アライグマの排泄物を安全に処理する方法は?【直接触れない】適切な防護具と5つの処理手順を解説

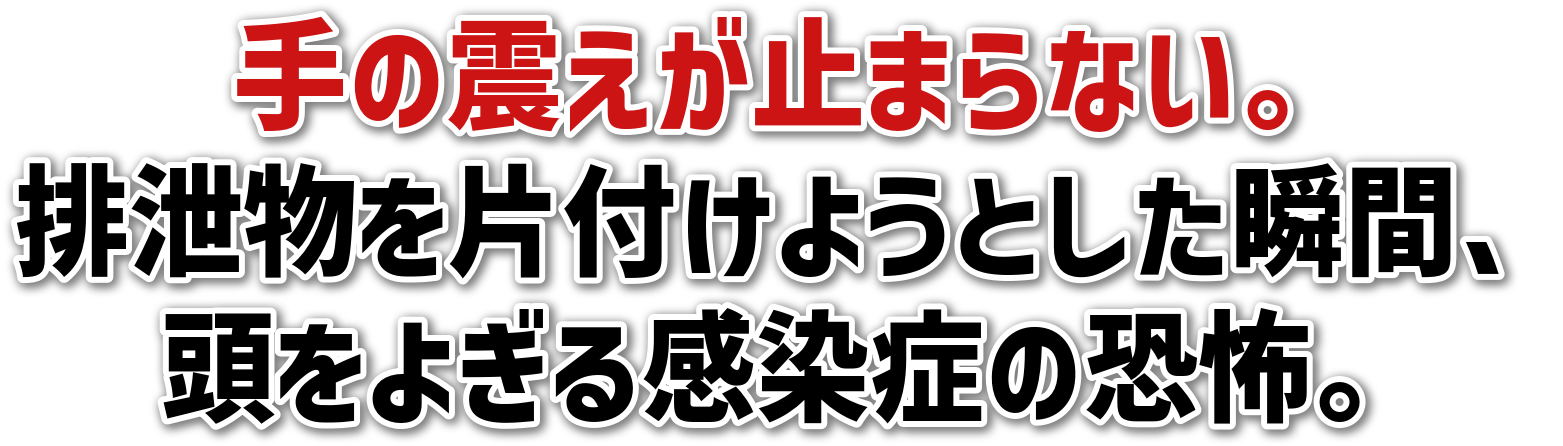
【この記事に書かれてあること】
アライグマの排泄物を見つけてしまった!- アライグマの排泄物は危険な感染症の原因に
- 直接触れないことが安全処理の基本
- 屋内外や排泄物の状態で処理方法が異なる
- 適切な防護具の使用が不可欠
- 身近な道具を活用した5つの安全処理法を紹介
でも、うっかり触ってしまうのは超危険です。
感染症のリスクが高いアライグマの排泄物、どう処理すればいいの?
「素手はダメ」なのはわかるけど、具体的な方法がわからなくてモヤモヤ…。
そんなあなたに朗報です!
今回は、身近な道具を使った5つの安全な処理法をご紹介します。
これさえ押さえれば、アライグマの排泄物処理もバッチリ。
家族やペットの健康を守りながら、スッキリ解決しちゃいましょう!
【もくじ】
アライグマの排泄物処理の基本と危険性

アライグマの排泄物が引き起こす「感染症リスク」
アライグマの排泄物は、深刻な感染症を引き起こす危険性があります。油断は禁物です。
アライグマの糞や尿には、人間や動物に感染する恐ろしい病原体がひそんでいます。
「え?ただの動物の糞尿でしょ?」なんて思っていませんか?
それが大間違い。
アライグマの排泄物は、ただの不快な汚れ物ではないんです。
- 細菌:サルモネラ菌や大腸菌などの食中毒の原因菌
- ウイルス:狂犬病ウイルスなどの致命的な病気の原因
- 寄生虫:アライグマ回虫など、重篤な症状を引き起こす危険な寄生虫
「ちょっと触ったくらいなら大丈夫」なんて考えは、とても危険です。
特に子どもやお年寄り、妊婦さんは感染のリスクが高くなります。
庭で遊ぶ子どもたちが知らずに触れてしまったら…想像しただけでゾッとしますよね。
アライグマの排泄物を見つけたら、すぐに適切な処理をすることが大切です。
放っておくと、病原体が増殖して周囲に広がり、感染のリスクがグングン高まっちゃうんです。
安全第一で、慎重に対処しましょう。
排泄物から感染する「アライグマ回虫症」の恐怖
アライグマ回虫症は、アライグマの排泄物から感染する恐ろしい病気です。油断は禁物、しっかり対策を。
「え?回虫って、子どもの頃に聞いたことあるけど、大したことないんじゃ…」なんて思っていませんか?
ところが、アライグマ回虫は普通の回虫とは比べものにならないくらい危険なんです。
アライグマ回虫の恐ろしさ、ご紹介しましょう。
- 目に見えないほど小さな卵が感染源
- 人間の体内で成虫にならず、幼虫のまま体内を移動
- 脳や目、肝臓などの重要な臓器に侵入する可能性
- 重症化すると失明や脳障害などの深刻な後遺症も
風で舞い上がったり、土や水に混ざったりして、知らないうちに口から体内に入ってしまうことも。
「見た目はキレイな場所だから大丈夫」なんて思っていても、実は危険が潜んでいるかもしれません。
感染すると、初期症状はかゆみや発熱程度。
でも、そのうち激しい頭痛や吐き気、けいれんなどの重い症状が現れることも。
治療が難しく、完治までに時間がかかることもあるんです。
「うちの庭にアライグマは来ないから…」なんて安心してはいけません。
都市部でもアライグマの生息が増えているんです。
排泄物を見つけたら、すぐに適切な処理を。
自分と家族の健康を守るため、油断は禁物です。
直接触れると危険!排泄物処理の「3つのNG行動」
アライグマの排泄物処理には、絶対にしてはいけない行動があります。危険を避けるため、3つのNG行動を覚えておきましょう。
まず、絶対にやってはいけないのが、素手で直接触ることです。
「ちょっとくらいなら…」なんて考えは危険です。
目に見えない病原体が、皮膚のちょっとした傷から侵入するかもしれません。
「えっ、そんな簡単に感染するの?」と思うかもしれませんが、実際にそうなんです。
次に注意したいのが、水をかけて流すこと。
一見、きれいになったように見えても、実は逆効果。
病原体を広範囲に拡散させてしまい、かえって危険な状況を作り出してしまいます。
「水で流せば解決!」なんて簡単に考えちゃダメです。
最後は、掃除機で吸い取ること。
これも絶対NGです。
排泄物が粉々になって、空気中に飛び散ってしまいます。
知らず知らずのうちに吸い込んでしまう可能性も。
「掃除機なら楽チン!」なんて思わないでくださいね。
では、正しい処理方法は?
ここがポイントです。
- 必ず手袋とマスクを着用
- 長袖、長ズボンで肌の露出を避ける
- 使い捨てのスコップやシャベルを使用
- 排泄物をビニール袋に密閉して廃棄
- 処理後は手や使用した道具を徹底的に消毒
自分と家族の健康を守るため、慎重な処理が大切です。
アライグマの排泄物、侮ってはいけません。
正しい知識と行動で、安全に対処しましょう。
正しい防護具の選び方と「完全防備」の重要性
アライグマの排泄物処理には、適切な防護具が欠かせません。正しい選び方と完全防備の重要性を押さえておきましょう。
まず、使い捨て手袋は必須アイテムです。
ゴム製やビニール製ではなく、ラテックスやニトリル製を選びましょう。
「え?普通のゴム手袋じゃダメなの?」と思うかもしれません。
でも、これらの素材は耐水性が高く、病原体からしっかり手を守ってくれるんです。
次に大切なのがマスクです。
ただし、普通の不織布マスクでは不十分。
N95規格以上の高性能マスクを使いましょう。
「そこまで必要?」と思うかもしれませんが、目に見えない危険な粒子から身を守るには、これくらいの性能が必要なんです。
目の保護も忘れずに。
防護メガネやゴーグルで、目への感染リスクを防ぎます。
「メガネをかけてるから大丈夫」なんて油断は禁物。
専用の防護具で、確実に目を守りましょう。
服装も重要です。
- 長袖の上着
- 長ズボン
- 靴下と靴(サンダルはNG)
「暑いから半袖で…」なんて妥協は危険です。
最後に、使い捨てのエプロンやつなぎがあれば、さらに安心。
「そこまでする?」と思うかもしれませんが、完全防備が一番の安全策なんです。
これらの防護具を正しく着用し、処理後は適切に廃棄または消毒することも忘れずに。
「面倒くさい…」なんて思わず、自分と家族の健康を守るため、しっかり備えましょう。
アライグマの排泄物処理、甘く見ないで。
完全防備で、安全第一に取り組むことが大切です。
アライグマの排泄物処理を徹底比較

屋内vs屋外!処理の難易度と注意点の違い
アライグマの排泄物処理は、屋内と屋外で難易度が大きく異なります。それぞれの特徴を押さえて、適切に対処しましょう。
まず、屋内での処理は一般的に難易度が高いです。
「え?屋内の方が簡単じゃないの?」って思われるかもしれませんが、そうではないんです。
屋内は閉鎖空間なので、排泄物の臭いや病原体が濃縮されやすいんです。
換気が難しい場合も多く、作業中に悪臭や有害物質を吸い込むリスクが高まります。
一方、屋外での処理は比較的やりやすいですが、油断は禁物です。
広い空間なので換気の心配はありませんが、周囲の環境への影響を考える必要があります。
- 屋内:換気に注意、周囲への汚染防止が重要
- 屋外:天候の影響を受けやすい、周辺の土壌も処理が必要
排泄物の周りにはビニールシートなどを敷いて、床や壁への汚染を防ぎましょう。
「ちょっとくらいいいか」なんて思わずに、しっかり対策を。
屋外では、雨や風の影響を受けやすいので、天気の良い日を選んで作業するのがおすすめです。
また、排泄物の周囲の土も一緒に処理する必要があります。
「見た目はきれいだから大丈夫」なんて油断は禁物。
目に見えない病原体が土壌に潜んでいる可能性があるんです。
どちらの場合も、適切な防護具の着用が欠かせません。
手袋、マスク、そして目を保護するゴーグルは必須です。
「面倒くさい…」なんて思わずに、しっかり身を守りましょう。
結局のところ、屋内外どちらの処理も一長一短。
それぞれの特徴を理解して、慎重に対処することが大切です。
安全第一で、アライグマの排泄物処理に臨んでくださいね。
乾燥した排泄物と新鮮な排泄物の処理法の違い
アライグマの排泄物、乾いているか新鮮かで処理方法が全然違うんです。それぞれの特徴を押さえて、適切に対処しましょう。
まず、乾燥した排泄物。
一見処理しやすそうに見えますが、実は要注意なんです。
「乾いてるから大丈夫でしょ」なんて思っていませんか?
それが大間違い。
乾燥すると軽くなって、ホコリのように舞い上がりやすくなるんです。
これが鼻や口から体内に入ると、大変なことに。
一方、新鮮な排泄物は見た目は気持ち悪いですが、意外と処理しやすいんです。
でも油断は禁物。
水分を含んでいるので、周囲に広がりやすい特徴があります。
- 乾燥排泄物:粉々になりやすい、舞い上がりやすい
- 新鮮排泄物:水分で周囲に広がりやすい、臭いが強い
これで舞い上がるのを防げます。
その後、ゆっくりとスコップですくい取りましょう。
「さっさと片付けちゃおう」なんて急いではダメですよ。
丁寧に、丁寧に。
新鮮排泄物は、まず周囲にトイレットペーパーや新聞紙を敷いて、広がるのを防ぎます。
そして、使い捨てのヘラやスコップでそっと掬い取ります。
「うわ、臭い!」って思わず顔を近づけたくなりますが、ガマンですよ。
どちらの場合も、二重にしたビニール袋に入れて密閉するのがポイント。
「一重で十分でしょ」なんて思わないでくださいね。
二重にすることで、万が一の破れにも対応できるんです。
処理後の消毒も忘れずに。
乾燥排泄物があった場所は、水拭きしてから消毒液で念入りに。
新鮮排泄物の場合は、まず水分をよく拭き取ってから消毒します。
結局のところ、乾燥・新鮮どちらの排泄物も油断大敵。
それぞれの特徴を理解して、慎重に対処することが大切です。
「面倒くさい」なんて思わずに、しっかり対策を。
あなたと家族の健康を守るため、頑張りましょう!
単発の処理と長期的な対策「どっちが効果的?」
アライグマの排泄物、単発で処理するだけで十分?それとも長期的な対策が必要?
結論から言うと、両方大切なんです。
でも、やっぱり長期的な対策の方が効果的です。
単発の処理は、目の前の問題を解決するには確かに有効。
「とりあえずキレイにしたい!」という気持ちはよくわかります。
でも、それだけじゃアライグマはまた来ちゃうんです。
つまり、いたちごっこになっちゃうわけ。
一方、長期的な対策は根本的な解決につながります。
アライグマが寄ってこないような環境づくりをすることで、排泄物の問題そのものを減らせるんです。
じゃあ、具体的にどんな違いがあるの?
比べてみましょう。
- 単発処理:即効性あり、でも再発の可能性大
- 長期対策:効果が出るまで時間がかかるが、持続的な解決につながる
例えば、庭で排泄物を見つけて処理したとしても、翌日にはまた同じ場所に…なんてことも。
「えー、また?」ってガッカリしちゃいますよね。
長期的な対策は、時間はかかりますが効果は大きいです。
例えば、庭に侵入しにくいフェンスを設置したり、餌になりそうな果物や野菜の管理を徹底したり。
「面倒くさそう…」って思うかもしれませんが、長い目で見ればこっちの方が楽になるんです。
理想的なのは、単発処理と長期対策を組み合わせること。
目の前の排泄物はしっかり処理しつつ、再発防止のための対策も同時に行う。
これが一番効果的なんです。
具体的には、こんな感じ。
- 排泄物を適切に処理する(単発処理)
- 処理した場所に忌避剤を撒く(長期対策の一歩)
- 庭全体の見直しを行い、アライグマが好む環境を減らす(本格的な長期対策)
でも、これを続けることで、アライグマの被害は確実に減っていきます。
最初は大変でも、長い目で見ればずっと楽になるんです。
結局のところ、単発処理と長期対策、どっちも大切。
でも、本当に効果を出したいなら、長期的な視点を持つことが重要です。
根気よく対策を続けて、アライグマとの平和な共存を目指しましょう!
素手での処理vs道具を使った処理「安全性の差」
アライグマの排泄物、素手で処理する?それとも道具を使う?
答えは一目瞭然、道具を使った処理が圧倒的に安全です。
でも、具体的にどれくらい違うのか、詳しく見ていきましょう。
まず、素手での処理。
「ちょっとくらいなら…」なんて思っていませんか?
それが大間違い。
素手で触れることは、感染症のリスクを著しく高めます。
アライグマの排泄物には、人間に感染する危険な病原体がうじゃうじゃいるんです。
ぞっとしますよね。
一方、道具を使った処理は安全性が格段に上がります。
直接触れることなく、病原体との接触を最小限に抑えられるんです。
では、具体的にどんな違いがあるのか、比べてみましょう。
- 素手処理:感染リスク極めて高い、皮膚から直接感染の可能性
- 道具処理:感染リスク大幅に低下、安全に処理可能
「大げさだなぁ」なんて思わないでください。
本当に危険なんです。
手の小さな傷から病原体が侵入したり、知らず知らずのうちに顔を触って口や鼻から感染したり。
考えただけでゾクゾクしますよね。
道具を使えば、こんな心配はグッと減ります。
長柄のスコップやトングを使えば、排泄物から安全な距離を保てます。
「へぇ、そんなに違うんだ」って驚くかもしれません。
でも、本当なんです。
特におすすめなのが、使い捨ての道具を活用すること。
例えば、厚手の紙皿をスコップ代わりに使ったり、段ボールを切って作った即席シャベルを使ったり。
使い終わったらそのまま排泄物と一緒に捨てられるので、二次感染のリスクも減らせます。
ただし、道具を使う場合でも油断は禁物。
必ず手袋とマスクは着用しましょう。
「面倒くさい…」なんて思わずに、しっかり身を守ることが大切です。
結局のところ、素手での処理と道具を使った処理、安全性に雲泥の差があります。
少し手間がかかっても、必ず道具を使いましょう。
あなたと家族の健康を守るため、安全第一で対処することが大切です。
アライグマの排泄物、甘く見ないでくださいね!
アライグマvs他の動物!排泄物処理の難しさ比較
アライグマの排泄物、他の動物と比べてどうなの?結論から言うと、アライグマの排泄物処理は格段に難しいんです。
でも、具体的にどう違うのか、詳しく見ていきましょう。
まず、アライグマの排泄物は感染症のリスクが極めて高いです。
「え?他の動物はいいの?」って思うかもしれません。
もちろん、他の動物の排泄物も注意は必要です。
でも、アライグマの場合は特に要注意なんです。
例えば、犬や猫の排泄物と比べてみましょう。
- アライグマ:複数の危険な感染症のリスクあり、寄生虫も多い
- 犬や猫:感染症リスクはあるが、一般的に管理されている
でも、野生のアライグマにそんな管理はありません。
様々な病気や寄生虫を持っている可能性が高いんです。
特に怖いのが、アライグマ回虫症。
これ、アライグマ特有の寄生虫が引き起こす病気なんです。
「回虫なんて、子供の頃聞いたな」なんて思っていませんか?
でも、アライグマ回虫は普通の回虫とは比べものにならないくらい危険なんです。
- 目や脳に寄生する可能性がある
- 重症化すると失明や脳障害の危険も
- 完治が難しく、長期の治療が必要になることも
だからこそ、アライグマの排泄物処理は特別な注意が必要なんです。
また、アライグマの排泄物は見分けるのも難しいです。
「え?うんちの見分けくらい…」って思うかもしれません。
でも、意外と難しいんです。
大きさや形が似ている動物もいるので、素人判断は危険です。
な注意が必要なんです。
結局のところ、アライグマの排泄物処理は他の動物と比べてかなり難しいんです。
感染症のリスクが高く、見分けるのも簡単ではありません。
「面倒くさい…」なんて思わずに、しっかり対策を立てることが大切です。
でも、難しいからこそ、proper(適切)に対処する意義も大きいんです。
あなたと家族の健康を守るため、アライグマの排泄物には特別な注意を払いましょう。
他の動物の排泄物よりも慎重に、でも恐れすぎずに。
正しい知識と適切な対策で、安全に処理することができるんです。
アライグマの排泄物、侮ってはいけません。
でも、過度に怖がる必要もありません。
正しい知識を身につけて、適切に対処すれば大丈夫。
頑張りましょう!
アライグマの排泄物を安全に処理する5つの裏技

使い古しの園芸用スコップで「簡単回収」テクニック
使い古しの園芸用スコップを活用すれば、アライグマの排泄物を安全かつ効率的に回収できます。この方法なら、直接触れずに処理できるんです。
「え?普通のスコップじゃダメなの?」って思うかもしれませんね。
実は、使い古しのスコップがおすすめなんです。
なぜかというと、万が一の汚染時に気兼ねなく捨てられるからです。
まず、スコップを選ぶときのポイントをご紹介します。
- 金属製よりもプラスチック製がおすすめ(軽くて扱いやすい)
- 柄の長さは30cm以上あると安全(排泄物から距離を取れる)
- 平らな刃先のものを選ぶ(土ごとすくいやすい)
- 排泄物の周りに新聞紙やビニールシートを敷く
- スコップで排泄物と周囲の土を一緒にすくい取る
- ビニール袋に直接入れる(袋は二重にすると安心)
- 使用したスコップは消毒するか、処分する
この方法なら、排泄物に直接触れることなく、安全に処理できるんです。
ここで重要なのが、周囲の土もしっかり回収すること。
見た目はきれいでも、目に見えない病原体が潜んでいる可能性があるんです。
「まあ、いいか」なんて油断は禁物ですよ。
回収後は、スコップをしっかり消毒しましょう。
塩素系漂白剤を薄めた溶液で洗い、よく乾かします。
でも、何度も使うよりは使い捨てにするのが一番安全。
「もったいない」って思うかもしれませんが、健康には代えられませんからね。
この方法で、アライグマの排泄物処理がグッと楽になりますよ。
安全第一で、頑張って対処しましょう!
ペットシーツを活用した「周囲の土ごと」処理法
ペットシーツを使えば、アライグマの排泄物を周囲の土ごと安全に処理できます。この方法なら、直接触れずに簡単に回収できるんです。
「ペットシーツ?それって犬や猫用じゃ…」って思いましたか?
実は、アライグマの排泄物処理にもピッタリなんです。
吸収力が高くて、処理後そのまま捨てられるから、とっても便利なんですよ。
では、具体的な手順を見ていきましょう。
- 排泄物の周りにペットシーツを敷く
- シーツの上から排泄物と周囲の土をのせる
- シーツの四隅を持ち上げて包み込む
- そのままビニール袋に入れて密閉
アライグマの排泄物は、周囲の土にも病原体が広がっている可能性があるんです。
「見た目はきれいだから大丈夫」なんて油断は禁物ですよ。
ペットシーツ選びのポイントも押さえておきましょう。
- 吸収力の高いものを選ぶ(尿も処理できて一石二鳥)
- サイズは大きめのものがおすすめ(作業がしやすい)
- においを軽減する機能付きだとなお良し(処理時の不快感を減らせる)
確かに、普通のビニール袋よりは高いかもしれません。
でも、安全性と便利さを考えれば、十分元が取れるんです。
使用後は、そのままゴミ袋に入れて捨てられるので、二次感染のリスクも低くなります。
「楽ちん」なだけじゃなく、安全面でもバッチリなんです。
この方法を使えば、アライグマの排泄物処理がぐっと楽になりますよ。
ちょっとした工夫で、安全で効率的な処理ができるんです。
ぜひ試してみてくださいね!
重曹やコーヒーの粉で「臭い対策」しながら処理
重曹やコーヒーの粉を使えば、アライグマの排泄物の臭いを抑えながら安全に処理できます。この方法なら、不快な臭いに悩まされずに作業できるんです。
「え?重曹やコーヒーの粉で本当に大丈夫?」って思いましたか?
大丈夫、これらは臭い消しの達人なんです。
しかも、家庭にあるものでできるから、すぐに実践できるんですよ。
まず、それぞれの特徴を見てみましょう。
- 重曹:吸着力が高く、酸性の臭いを中和
- コーヒーの粉:強い香りで臭いをマスキング
排泄物の周りに重曹やコーヒーの粉をふりかけるだけ。
すると、ふわっと広がる嫌な臭いがグッと抑えられるんです。
「へぇ、こんな簡単なの?」って驚くかもしれませんね。
具体的な手順はこんな感じです。
- 排泄物の周りに重曹やコーヒーの粉をたっぷりまく
- 5?10分ほど置いて、臭いを吸着させる
- その後、通常の方法で排泄物を回収
- 使用した重曹やコーヒーの粉も一緒に処分
臭いで気分が悪くなることなく、落ち着いて処理できるんです。
「ああ、これなら頑張れそう」って思えますよね。
ただし、注意点もあります。
重曹やコーヒーの粉は、あくまで臭い対策。
病原体を殺菌するわけではないんです。
だから、処理後の消毒はしっかり行う必要があります。
「臭いがなくなったからもういいや」なんて油断は禁物ですよ。
それから、アレルギーがある人は使用を控えましょう。
特にコーヒーの粉は、アレルギー反応を引き起こす可能性があるんです。
「えっ、そんなことまで?」って思うかもしれませんが、安全第一が大切なんです。
この方法を使えば、アライグマの排泄物処理がぐっと楽になりますよ。
臭いストレスから解放されて、スムーズに作業できるんです。
ぜひ試してみてください!
段ボールで「乾燥&固形化」させる回収術
段ボールを使えば、アライグマの排泄物を乾燥させて固形化し、安全に回収できます。この方法なら、飛散のリスクを減らして処理できるんです。
「段ボール?それって本当に効果あるの?」って思いましたか?
実は、段ボールには驚くほどの吸水性があるんです。
それを利用して、排泄物を扱いやすい状態にするんですよ。
では、具体的な手順を見ていきましょう。
- 排泄物の上に適当な大きさの段ボールを被せる
- 段ボールの上から重しを置く
- 30分?1時間ほど放置
- 段ボールごと排泄物を回収
液状だと飛び散りやすい排泄物も、固まれば扱いやすくなるんです。
「なるほど、そういうことか」って納得できますよね。
段ボールを選ぶときのコツもあります。
- 厚手のものを選ぶ(吸水性が高い)
- 波形の部分が多いものがおすすめ(乾燥効果が高い)
- 排泄物より一回り大きいサイズを使う(はみ出さない)
確かに、その可能性はあります。
だから、重曹やコーヒーの粉を一緒に使うのもおすすめです。
臭い対策もバッチリですよ。
注意点としては、風の強い日は避けること。
段ボールが飛ばされて、かえって被害が広がる可能性があるんです。
「そんなことまで考えるの?」って思うかもしれませんが、細心の注意が大切なんです。
それから、雨の日もNGです。
水分で段ボールが崩れてしまい、効果が半減しちゃいます。
天気のいい日を選んで作業するのがコツです。
この方法を使えば、アライグマの排泄物処理がぐっと安全になりますよ。
飛散のリスクを減らして、安心して作業できるんです。
工夫次第で、厄介な作業も楽になるんですね。
頑張って対処しましょう!
小麦粉で「湿気を吸収」させる処理テクニック
小麦粉を使えば、アライグマの排泄物の湿気を吸収させて、安全に処理できます。この方法なら、べたべたした排泄物も扱いやすくなるんです。
「え?小麦粉?料理に使うあれ?」って驚いたかもしれませんね。
実は、小麦粉には優れた吸水性があるんです。
それを利用して、排泄物を乾燥させるんですよ。
では、具体的な手順を見ていきましょう。
- 排泄物の上に小麦粉をたっぷりふりかける
- 5?10分ほど放置
- スコップなどで固まった排泄物を回収
- 使用した小麦粉も一緒に処分
べたべたした状態だと回収が難しいですよね。
でも、小麦粉で固めれば、ずっと扱いやすくなるんです。
小麦粉の選び方にもコツがあります。
- 薄力粉よりも強力粉の方が吸水性が高い
- 新しいものよりも古いものの方が吸水性が増している
- できれば賞味期限の切れたものを使うと経済的
確かに、食べ物を無駄にするのは良くありません。
だからこそ、賞味期限の切れたものを使うのがおすすめなんです。
「なるほど、そういう使い方があるんだ」って気づきますよね。
注意点としては、風の強い日は避けること。
小麦粉が舞い上がって、かえって周囲を汚してしまう可能性があるんです。
「そこまで考えるの?」って思うかもしれませんが、細かい配慮が大切なんです。
それから、アレルギーのある人は使用を控えましょう。
小麦アレルギーの方にとっては危険な方法になってしまいます。
安全第一で、別の方法を選ぶのが賢明です。
この方法を使えば、アライグマの排泄物処理がぐっと楽になりますよ。
べたべたした排泄物も、サクッと回収できるんです。
身近なものでこんなに便利な対策ができるなんて、すごいですよね。
ぜひ試してみてください!