アライグマ捕獲後の適切な対処方法は?【素手での取り扱いは厳禁】安全な保管と連絡手順を5つのステップで紹介

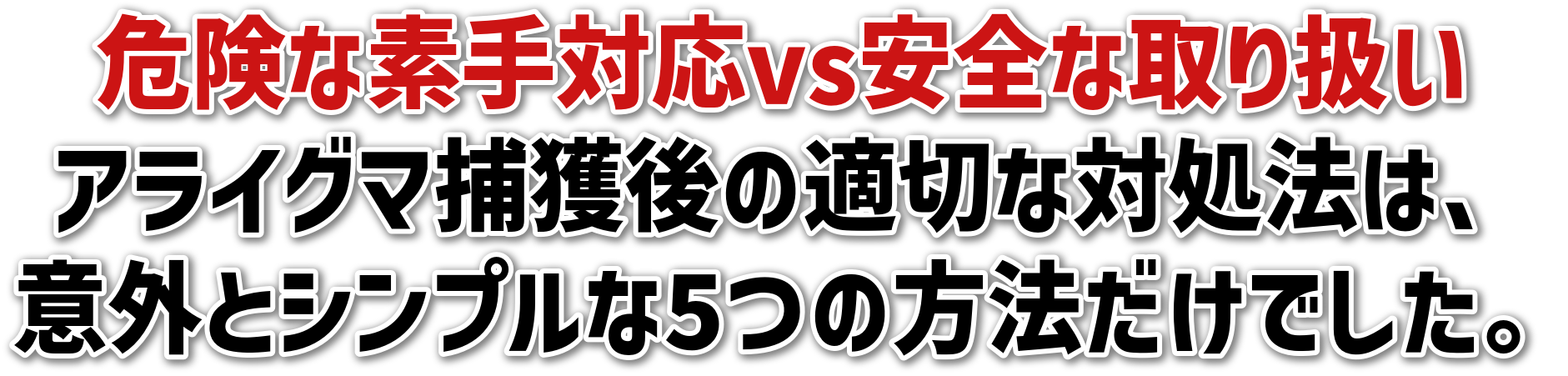
【この記事に書かれてあること】
アライグマを捕獲した!- アライグマ捕獲後は素手での取り扱いを絶対に避ける
- 捕獲したアライグマの一時保管には専用の場所が必要
- 関係機関への連絡は捕獲後速やかに行うことが重要
- 自己判断での再放獣は生態系への悪影響を引き起こす可能性がある
- アライグマ対策には意外な材料を使った驚きの方法がある
でも、その後どうすればいいの?
実は、捕獲後の対応を間違えると大変なことになるんです。
感染症のリスクや生態系への影響など、様々な問題が潜んでいます。
でも、大丈夫。
適切な対処法を知れば怖くありません。
この記事では、アライグマ捕獲後の安全な取り扱い方から、意外な撃退法まで、詳しく解説します。
捕獲したアライグマと上手に付き合う方法、一緒に学んでいきましょう!
【もくじ】
アライグマ捕獲後の適切な対処とは

素手での取り扱いは絶対NG!感染症リスクに注意
捕獲したアライグマを素手で扱うのは絶対にやめましょう。感染症のリスクが高く、大変危険です。
アライグマを捕まえた!
でも、ちょっと待ってください。
「かわいそうだから早く逃がしてあげよう」なんて考えていませんか?
それは大間違いです。
アライグマは見た目は愛らしいですが、実は危険な野生動物なんです。
まず、アライグマは様々な感染症を持っている可能性があります。
例えば、狂犬病やアライグマ回虫症などです。
これらの病気は人間にも感染する可能性があり、とても怖いものなんです。
「でも、ちょっと触るくらいなら大丈夫でしょ?」なんて思っていませんか?
それが危険なのです。
アライグマの爪や歯には細菌がいっぱい。
ほんの小さな傷からでも感染症にかかる可能性があるんです。
では、どうすればいいのでしょうか?
アライグマを安全に扱うために、次の3つの点に気をつけましょう。
- 必ず厚手の革手袋を着用する
- 長袖の作業着と長靴を身につける
- 目を守るためにゴーグルをかける
さらに、アライグマを扱う際はゆっくりと慎重に行動しましょう。
急な動きは動物を驚かせ、攻撃的になる可能性があります。
アライグマの捕獲後の対処は、専門家に任せるのが一番安全です。
でも、どうしても自分で対応しなければならない場合は、しっかりと防護して慎重に行動することが大切なんです。
捕獲したアライグマの一時保管「3つの重要ポイント」
捕獲したアライグマを一時的に保管する場合、安全と衛生面に気をつけた対応が必要です。3つの重要ポイントを押さえましょう。
アライグマを捕まえたはいいけれど、すぐに処分できない…。
そんな時、どうすればいいのでしょうか?
一時保管が必要になることもありますよね。
でも、ただ置いておけばいいというわけではありません。
アライグマの安全と周囲の環境を考えた対応が大切なんです。
まず、3つの重要ポイントを覚えておきましょう。
- 風通しの良い日陰に置く
- 水と餌を与える
- 人や他の動物が近づかない場所を選ぶ
1つ目は、風通しの良い日陰に置くことです。
アライグマは体温調節が苦手なので、直射日光を避けるのが大切。
「エアコンの効いた部屋に入れてあげよう」なんて考えていませんか?
それは逆効果です。
自然な環境に近い場所がベストなんです。
2つ目は、水と餌を与えることです。
「捕まえたんだから、餌なんてあげなくていいでしょ」なんて思っていませんか?
それは間違いです。
一時保管中もアライグマの健康を維持することが大切なんです。
水はたっぷりと、餌は少量でOKです。
3つ目は、人や他の動物が近づかない場所を選ぶことです。
これは、アライグマのストレスを軽減するためだけでなく、周囲の安全を守るためでもあります。
「でも、家の中には置けないし…」と困っていませんか?
大丈夫です。
庭の隅や物置など、人の出入りが少ない場所を選びましょう。
もし、そういった場所がない場合は、捕獲用のケージにタオルをかけて、刺激を減らすのも良い方法です。
一時保管中も、アライグマの様子をこまめに観察することを忘れずに。
異常があれば、すぐに専門家に相談しましょう。
関係機関への連絡は「速やかに」が鉄則!
アライグマを捕獲したら、すぐに地域の自治体や保健所に連絡することが大切です。速やかな連絡が適切な対応につながります。
「やった!アライグマを捕まえたぞ」そんな喜びもつかの間、次は何をすればいいのでしょうか?
実は、捕獲後の行動がとても重要なんです。
その中でも、関係機関への連絡は絶対に忘れてはいけません。
でも、「誰に連絡すればいいの?」「何を伝えればいいの?」と疑問に思う人も多いはず。
大丈夕、順を追って説明しますね。
まず、連絡先ですが、地域の自治体や保健所が基本です。
多くの場合、市役所や町役場の環境課や農林課が担当していることが多いですよ。
事前に調べておくと安心ですね。
次に、いつ連絡するべきかですが、答えは「すぐに」です。
捕獲後、できるだけ早く連絡しましょう。
「明日の朝でいいかな」なんて思っていませんか?
それは危険です。
アライグマは夜行性なので、夜中に暴れ出す可能性があるんです。
では、連絡する際にはどんな情報を伝えればいいのでしょうか?
以下の4点を忘れずに伝えましょう。
- 捕獲した場所
- 捕獲した日時
- アライグマの状態(大きさ、怪我の有無など)
- 現在の保管場所
「でも、休日だったら…」と心配になりませんか?
大丈夕です。
多くの自治体では、緊急連絡先を設けています。
事前に調べておくと、いざという時に慌てずに済みますよ。
最後に、一つアドバイス。
関係機関に連絡したら、その指示に従うことが大切です。
「自分で何とかしよう」なんて考えるのは禁物。
プロの指示に従うことで、安全かつ適切な対応ができるんです。
関係機関への速やかな連絡、忘れずにね。
それが、アライグマ問題を解決する第一歩になるんです。
自己判断での再放獣はNG!「生態系への影響」に注意
捕獲したアライグマを自己判断で別の場所に放すのは絶対にやめましょう。生態系への悪影響が大きく、法律違反になる可能性もあります。
「かわいそうだから、山に逃がしてあげよう」なんて考えていませんか?
それは大間違いです。
一見優しい行動に思えるかもしれませんが、実は大きな問題を引き起こす可能性があるんです。
まず、アライグマは外来生物。
もともと日本にいなかった動物なんです。
それを新しい場所に放すと、どうなるでしょうか?
そう、新たな被害が始まってしまうんです。
例えば、こんな影響が考えられます。
- 地域の農作物への被害拡大
- 在来種(もともとその地域にいる動物)の減少
- 生態系のバランスの崩れ
それが危険なんです。
アライグマは繁殖力が強く、あっという間に数が増えてしまいます。
一匹が引き起こす問題は、想像以上に大きいんです。
さらに、自己判断での再放獣は法律違反になる可能性もあります。
「えっ、そんなの知らなかった!」とびっくりした人もいるでしょう。
でも、外来生物法という法律では、アライグマを勝手に運搬したり放したりすることを禁止しているんです。
じゃあ、どうすればいいの?
答えは簡単です。
必ず専門家や関係機関に相談しましょう。
彼らは適切な処置方法を知っていますし、法律に沿った対応をしてくれます。
「でも、殺されちゃうんじゃ…」と心配になる人もいるかもしれません。
確かに、命を奪うのは辛いことです。
でも、一匹の命と地域全体の生態系、どちらを守るべきでしょうか?
時には、難しい決断が必要なこともあるんです。
アライグマの問題は、一人で抱え込まず、みんなで考えていく必要があります。
自己判断での再放獣はNG。
それを覚えておけば、きっと正しい対応ができるはずです。
アライグマ捕獲後の対応「やってはいけない3つのこと」
アライグマ捕獲後の対応には注意が必要です。特に、絶対にやってはいけない3つのことを覚えておきましょう。
間違った対応は大きな問題を引き起こす可能性があります。
「やった!アライグマを捕まえたぞ」そんな喜びの声が聞こえてきそうですね。
でも、ちょっと待ってください。
捕獲後の対応を間違えると、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があるんです。
ここでは、絶対にやってはいけない3つのことを紹介します。
これさえ覚えておけば、大きな失敗は避けられるはずです。
- 素手で触る
- 自己判断で再放獣する
- ペットとして飼育する
これは絶対にNGです。
「でも、ちょっとだけなら…」なんて考えていませんか?
それが危険なんです。
アライグマは様々な病気を持っている可能性があります。
ほんの小さな傷からでも感染する可能性があるんです。
2つ目は、自己判断で再放獣すること。
「かわいそうだから、山に逃がしてあげよう」なんて思っていませんか?
それは大きな間違いです。
新たな場所で被害が広がる可能性があるんです。
しかも、法律違反になる可能性もあります。
3つ目は、ペットとして飼育すること。
「こんなにかわいいんだから、飼っちゃおう!」なんて考えるのは禁物です。
アライグマは野生動物。
ペットとして飼育するのは違法なんです。
しかも、成長すると凶暴になる可能性もあります。
「えっ、そんなにダメなことばかりなの?」と思った人もいるでしょう。
でも、これらの行動を避けることで、自分自身の安全も、地域の環境も守ることができるんです。
では、どうすればいいの?
答えは簡単です。
捕獲したら、すぐに地域の自治体や保健所に連絡しましょう。
彼らが適切な対応をしてくれるはずです。
アライグマ捕獲後の対応、難しく感じるかもしれません。
でも、この3つのNGポイントを覚えておけば、大丈夫。
正しい対応で、みんなが安心して暮らせる環境を守りましょう。
アライグマ捕獲後の安全な取り扱い方法

成獣vs幼獣「対応の難しさ」を比較!
成獣のアライグマの方が、幼獣よりも対応が難しいです。攻撃性が高く、力も強いため、より慎重な取り扱いが必要です。
「えっ、子どものアライグマの方が扱いやすいの?」そう思った方もいるかもしれませんね。
確かに、見た目は幼獣の方が小さくて可愛らしいです。
でも、アライグマの対応では、成獣の方が格段に難しいんです。
まず、成獣の特徴を見てみましょう。
- 体が大きく、力が強い
- 警戒心が強く、攻撃的になりやすい
- 経験豊富で、人間の行動を予測しやすい
- 体が小さく、力も弱い
- 好奇心旺盛で、警戒心が薄い
- 経験が少なく、人間の行動を予測しにくい
それが危険なんです。
確かに力は弱いですが、幼獣でも鋭い歯と爪を持っています。
油断は禁物です。
成獣の対応で特に注意が必要なのは、その予測不可能な行動です。
ガウッと突然噛みついてきたり、ガシャンと檻を揺らしたりと、想像以上に激しい反応をすることがあります。
「うわっ、こんなに暴れるなんて!」そんな驚きの声が聞こえてきそうです。
対応の難しさを例えるなら、成獣は荒波の海、幼獣は穏やかな湖といったところでしょうか。
荒波に立ち向かうには、より多くの経験と知識が必要になるんです。
ただし、幼獣だからといって油断は禁物。
どちらの場合も、適切な防護具の着用と慎重な対応が欠かせません。
アライグマとの格闘は、まるで綱渡りのようなもの。
一歩間違えば大変なことになっちゃいます。
安全第一で対応しましょう。
都市部vs農村部「アライグマ対応の違い」に注目
都市部でのアライグマ対応の方が、農村部よりも難しい傾向があります。周辺環境への配慮や、住民の理解を得ることが重要になるためです。
「えっ、都会の方が大変なの?」そう思った方も多いのではないでしょうか。
確かに、一見すると自然豊かな農村部の方が、アライグマとの遭遇機会は多そうです。
でも、実は都市部での対応の方が複雑なんです。
都市部でのアライグマ対応の特徴を見てみましょう。
- 人口密度が高く、近隣住民への配慮が必要
- 建物や構造物が多く、アライグマの隠れ場所が豊富
- 食べ物の残渣が多く、アライグマを引き寄せやすい
- 人口密度が低く、作業スペースに余裕がある
- 自然環境が豊かで、アライグマの生態を理解しやすい
- 農作物被害が主で、対策の必要性への理解が得やすい
「あっちこっちに逃げ道があって、大変そう!」そんな声が聞こえてきそうです。
特に注意が必要なのは、住民の理解を得ることです。
「えっ、うちの近所にアライグマがいるの?」「捕獲って、かわいそうじゃない?」など、様々な意見が飛び交います。
丁寧な説明と、安全への配慮が欠かせません。
農村部では、広々とした畑でアライグマを追いかけるイメージ。
「のびのびと作業できそう」と思う方もいるでしょう。
確かに、作業スペースの確保は比較的容易です。
ただし、農村部でも油断は禁物。
広大な自然は、アライグマにとっても格好の隠れ家。
ザザッと茂みに隠れられたら、見つけるのは至難の技です。
都市部も農村部も、それぞれに難しさがあります。
でも、どちらの場合も、地域の特性を理解し、適切な対策を講じることが大切。
アライグマ対策は、まるで地域ぐるみのかくれんぼ。
みんなで協力して、アライグマに勝とう!
アライグマvs他の野生動物「捕獲後の対応の複雑さ」を比較
アライグマの捕獲後の対応は、他の野生動物と比べてより複雑です。高い知能と器用な手先、そして逃走のリスクの高さが、対応を難しくしています。
「えっ、アライグマってそんなに大変なの?」と思った方もいるでしょう。
確かに、クマやイノシシなど、もっと大きな動物の方が怖そうに見えますよね。
でも、アライグマの対応は意外と厄介なんです。
アライグマと他の野生動物の捕獲後の対応を比べてみましょう。
- アライグマ:高い知能、器用な手先、強い好奇心
- 他の野生動物:本能的な行動が主、人間を恐れる傾向
「よし、檻を開けよう」とガチャガチャと器用に鍵を操作したり、「ここから逃げられそう」とキョロキョロと周囲を観察したりします。
「まるで脱出ゲームを楽しんでいるみたい!」なんて声が聞こえてきそうです。
一方、他の野生動物は比較的単純。
怖がって固まったり、ただがむしゃらに暴れたりすることが多いんです。
アライグマの器用な手先も要注意。
まるでマジシャンのように、思わぬところから脱出を試みます。
「えっ、そんな小さな隙間から出られるの?」なんて驚くこともしばしば。
逃走のリスクも高いんです。
アライグマは小回りが利き、高い運動能力を持っています。
ちょっとした隙を見せると、スルッと逃げ出してしまいます。
他の野生動物の場合、大きさや動きの特徴から、ある程度予測がつきやすいんです。
でも、アライグマは予測不能。
まるで忍者のように、思わぬ動きで驚かせてきます。
だからこそ、アライグマの捕獲後の対応には特別な注意が必要なんです。
「よし、しっかり対策しよう!」そんな心構えで臨むことが大切です。
アライグマとの知恵比べ、負けないように頑張りましょう!
捕獲直後vs数時間後「アライグマの状態変化」に要注意
アライグマの状態は、捕獲直後と数時間後で大きく変化します。最初は興奮状態ですが、時間とともに落ち着いてきます。
この変化を理解し、適切に対応することが重要です。
「えっ、時間で変わるの?」そう思った方もいるでしょう。
でも、アライグマも生き物。
捕まった直後と、しばらく経ってからでは、全然様子が違うんです。
まず、捕獲直後のアライグマの様子を見てみましょう。
- 激しく暴れる
- 大きな鳴き声を上げる
- 攻撃的な態度を取る
「わー、すごい迫力!」と驚くかもしれません。
一方、数時間後はどうでしょうか。
- 動きが落ち着く
- 鳴き声が小さくなる
- 警戒しつつも、周囲を観察する
この変化は、アライグマの対応にとって重要なポイントなんです。
捕獲直後は興奮して危険ですが、数時間後なら比較的安全に扱えるかもしれません。
でも、油断は禁物。
アライグマは賢い動物です。
落ち着いたふりをして、スキを狙っているかもしれません。
「よし、人間が油断したぞ」とガバッと飛びかかってくることだってあるんです。
時間経過による変化を、例えで表現してみましょう。
捕獲直後のアライグマは、まるでお祭りの太鼓のよう。
ドンドンと激しい音を立てます。
一方、数時間後は静かな湖のよう。
表面は穏やかですが、水面下では何が起きているかわかりません。
だからこそ、常に警戒を怠らないことが大切です。
時間が経っても、決して油断せず、安全な距離を保ちましょう。
アライグマの状態変化を理解することで、より安全で効果的な対応が可能になります。
「よし、じっくり観察しよう」そんな気持ちで、アライグマの変化を見守ってくださいね。
昼間vs夜間「捕獲時間帯による対応の違い」を解説
アライグマの捕獲時間帯によって、対応方法が大きく異なります。夜行性のアライグマは、昼間より夜間の方が活発で警戒心が強くなります。
時間帯に応じた適切な対応が求められます。
「えっ、時間帯で対応が変わるの?」と驚いた方もいるでしょう。
でも、アライグマは夜行性。
昼と夜では、まるで別の動物のように振る舞うんです。
まず、昼間に捕獲した場合の特徴を見てみましょう。
- 比較的おとなしい
- 眠そうな様子が多い
- 動きが鈍い
「ふわぁ、眠いニャ」なんて言いそうな雰囲気です。
一方、夜間の捕獲ではどうでしょうか。
- 非常に活発で敏感
- 素早い動きをする
- 警戒心が強い
キビキビと動き回ります。
この違いは、アライグマへの対応に大きく影響します。
昼間なら、比較的落ち着いて作業できるかもしれません。
でも夜は要注意。
ちょっとしたスキを見せると、ガバッと飛びかかってくる可能性があります。
特に気をつけたいのが、夜間の視界の問題です。
人間の目は夜に弱いですが、アライグマは得意中の得意。
「えっ、こんな暗いところでよく見えるね!」なんて驚くほど、夜目が利くんです。
昼間の捕獲は、まるで晴れた日のピクニックのよう。
ゆったりと対応できます。
一方、夜間の捕獲は、暗闇の鬼ごっこ。
緊張感たっぷりです。
ただし、昼間だからといって油断は禁物。
突然、ガバッと目を覚まして暴れだすこともあります。
常に警戒を怠らないことが大切です。
時間帯に関わらず、安全な距離を保ち、適切な防護具を着用することが重要です。
アライグマとの対応は、まるで24時間営業のコンビニ店員のよう。
いつでも適切な対応ができるよう、準備を整えておきましょう。
アライグマ被害を防ぐ5つの驚きの対策法

コーヒーの粉でアライグマの嗅覚を「混乱」させる!
コーヒーの粉を使うと、アライグマの鋭い嗅覚を混乱させ、効果的に撃退できます。「えっ、コーヒーの粉でアライグマが撃退できるの?」そう思った方も多いでしょう。
実は、コーヒーの強い香りがアライグマの嗅覚を混乱させるんです。
アライグマは鋭い嗅覚を持っています。
その嗅覚を利用して餌を探したり、危険を察知したりしているんです。
でも、コーヒーの強烈な香りに出会うと、その嗅覚がパニックに陥っちゃうんです。
使い方は簡単!
次の3つのステップを踏むだけです。
- 使用済みのコーヒーの粉を乾燥させる
- 乾燥させた粉を小さな布袋に入れる
- アライグマが出没する場所に置く
大丈夕です。
むしろ、身近にあるものだからこそ、すぐに実践できるんです。
コーヒーの粉を置く場所は、アライグマの侵入経路や好みの場所を考えて選びましょう。
例えば、ゴミ箱の周りや庭の入り口などがおすすめです。
「ふむふむ、なるほど」と納得していただけたでしょうか。
コーヒーの香りで人間はリラックスしますが、アライグマにとっては大問題なんです。
まるで、人間が強烈な臭いの部屋に閉じ込められたような感覚かもしれません。
ただし、注意点もあります。
雨に濡れると効果が薄れてしまうので、定期的に交換することをお忘れなく。
また、ペットがいる家庭では、ペットが誤って食べないよう配置に気をつけましょう。
コーヒーの粉、意外と強力な武器になるんです。
アライグマ対策、これで一歩前進ですね!
アンモニア臭の洗剤で「撃退効果」アップ!
アンモニア臭のする洗剤を使って庭を掃除すると、アライグマを効果的に寄せ付けなくすることができます。「えっ、掃除するだけでアライグマ対策になるの?」そう思った方も多いでしょう。
実は、アンモニアの強烈な臭いがアライグマを撃退するんです。
アライグマは鋭い嗅覚の持ち主。
その嗅覚を利用して、餌を探したり危険を察知したりしています。
アンモニア臭は、アライグマにとって非常に不快な臭いなんです。
まるで、人間が腐った卵の臭いを嗅がされているようなものかもしれません。
では、具体的な方法を見ていきましょう。
- アンモニア臭のする洗剤を水で薄める
- 薄めた洗剤で庭の地面や塀を拭く
- 特にアライグマが侵入しそうな場所を重点的に掃除する
確かに強い臭いですが、屋外で使用するので問題ありません。
むしろ、その強烈な臭いこそが効果の秘訣なんです。
掃除をする場所は、アライグマの侵入経路を考えて選びましょう。
例えば、庭の入り口や塀の周り、ゴミ置き場の近くなどがおすすめです。
「なるほど、掃除しながら対策できるんだ」と納得していただけたでしょうか。
一石二鳥ですよね。
庭がきれいになりつつ、アライグマも寄せ付けなくなるんです。
ただし、注意点もあります。
アンモニア臭は人間にとっても強烈な臭いです。
使用する際は、マスクを着用するなど、自身の健康にも気をつけましょう。
また、ペットがいる家庭では、ペットへの影響も考慮する必要があります。
アンモニア臭の洗剤、意外と強力な武器になるんです。
掃除しながらアライグマ対策、一石二鳥の効果を実感してくださいね!
風船設置で「アライグマを警戒」させる意外な方法
風船を庭に設置すると、その動きがアライグマを警戒させ、寄せ付けなくなります。意外ですが、効果的な対策方法なんです。
「えっ、風船でアライグマが怖がるの?」そう思った方も多いでしょう。
実は、風で揺れる風船の動きが、アライグマにとっては不気味で怖い存在なんです。
アライグマは警戒心が強い動物です。
見慣れない物や予測できない動きを見ると、すぐに警戒モードに入ります。
風船は風に揺られてフワフワと動くので、アライグマにとっては正体不明の怪しい物体。
「うわっ、なんだあれ!」って感じでしょうか。
では、具体的な方法を見ていきましょう。
- 大きめの風船を用意する(色は明るい色がおすすめ)
- 風船に紐をつけて、庭の木や柵に結ぶ
- 風船が風で自由に動けるよう、適度な長さの紐にする
- 複数の風船を庭の各所に配置する
確かにその通りです。
だからこそ、定期的にチェックして、しぼんだ風船は新しいものに交換することが大切です。
風船を置く場所は、アライグマの侵入経路を考えて選びましょう。
例えば、庭の入り口や、アライグマが頻繁に現れる場所などがおすすめです。
「なるほど、こんな簡単なことでいいんだ」と驚いた方も多いのではないでしょうか。
実は、シンプルな方法こそ効果的なことが多いんです。
ただし、注意点もあります。
強風の日は風船が飛ばされてしまう可能性があるので、天候には気をつけましょう。
また、小さな子どもやペットがいる家庭では、誤って風船を口に入れないよう注意が必要です。
風船、意外と強力なアライグマ撃退アイテムなんです。
カラフルな風船で庭を飾りつつ、アライグマ対策。
一石二鳥の効果を楽しんでくださいね!
ペパーミントオイルの「強烈な香り」でアライグマを遠ざける
ペパーミントオイルの強烈な香りを利用すると、アライグマを効果的に遠ざけることができます。自然な方法で、しかも爽やかな香りで家の周りを守れるんです。
「えっ、ハッカ油でアライグマが逃げるの?」そう思った方も多いでしょう。
実は、ペパーミントの強烈な香りがアライグマの鋭い嗅覚を刺激し、不快に感じさせるんです。
アライグマは嗅覚が非常に発達しています。
その鋭い嗅覚を利用して餌を探したり、危険を察知したりしているんです。
ペパーミントの強い香りは、アライグマにとってはまるで催涙ガスのような効果があるんです。
「くしゃみが止まらない!」って感じでしょうか。
では、具体的な使い方を見ていきましょう。
- ペパーミントオイルを用意する
- 綿球や布切れにオイルを数滴たらす
- オイルをしみこませた綿球や布を、小さな容器に入れる
- 容器をアライグマが出没する場所に置く
確かにその通りです。
だからこそ、置く場所や量を調整することが大切です。
人間が快適に過ごせる程度の香りで、アライグマには効果があるんです。
ペパーミントオイルを置く場所は、アライグマの侵入経路を考えて選びましょう。
例えば、庭の入り口や、ゴミ置き場の近く、家の周りなどがおすすめです。
「なるほど、爽やかな香りで対策できるんだ」と納得していただけたでしょうか。
まさに一石二鳥ですよね。
家の周りが良い香りになりつつ、アライグマも寄せ付けなくなるんです。
ただし、注意点もあります。
ペパーミントオイルは原液のまま直接皮膚につけると刺激が強すぎるので、取り扱いには気をつけましょう。
また、ペットがいる家庭では、ペットへの影響も考慮する必要があります。
ペパーミントオイル、意外と強力なアライグマ撃退アイテムなんです。
爽やかな香りで家を守る、新しいアライグマ対策を試してみてはいかがでしょうか。
古いCDの反射光で「アライグマを怖がらせる」驚きの技
古いCDを木に吊るすと、その反射光がアライグマを怖がらせ、近づきにくくなります。簡単で効果的、しかもリサイクルにもなる驚きの対策法です。
「えっ、CDでアライグマが怖がるの?」そう思った方も多いでしょう。
実は、CDの表面が反射する光が、アライグマにとっては不気味で怖い存在なんです。
アライグマは夜行性の動物です。
暗闇では目がよく見えるのですが、突然の光には弱いんです。
CDが反射する光は、アライグマにとってはまるで閃光弾のよう。
「うわっ、まぶしい!」って感じでしょうか。
では、具体的な方法を見ていきましょう。
- 使わなくなった古いCDを集める
- CDに穴を開けて、紐を通す
- CDを庭の木や柵に吊るす
- 風で自由に動くよう、適度な長さの紐にする
- 複数のCDを庭の各所に配置する
確かにその通りです。
だからこそ、定期的にチェックして、割れたり傷ついたりしたCDは新しいものに交換することが大切です。
CDを吊るす場所は、アライグマの侵入経路を考えて選びましょう。
例えば、庭の入り口や、アライグマが頻繁に現れる場所、月明かりが当たりやすい場所などがおすすめです。
「なるほど、こんな身近なもので対策できるんだ」と驚いた方も多いのではないでしょうか。
実は、アライグマ対策には意外と身近なものが役立つんです。
ただし、注意点もあります。
強風の日はCDが飛ばされてしまう可能性があるので、天候には気をつけましょう。
また、反射光が近隣の家に迷惑をかけないよう、配置には気を配る必要があります。
古いCD、意外と強力なアライグマ撃退アイテムなんです。
キラキラ光るCDで庭を飾りつつ、アライグマ対策。
一石二鳥の効果を楽しんでくださいね!