アライグマがメダカを食べる?【夜間の池が狙われやすい】効果的な池の保護方法3つを紹介

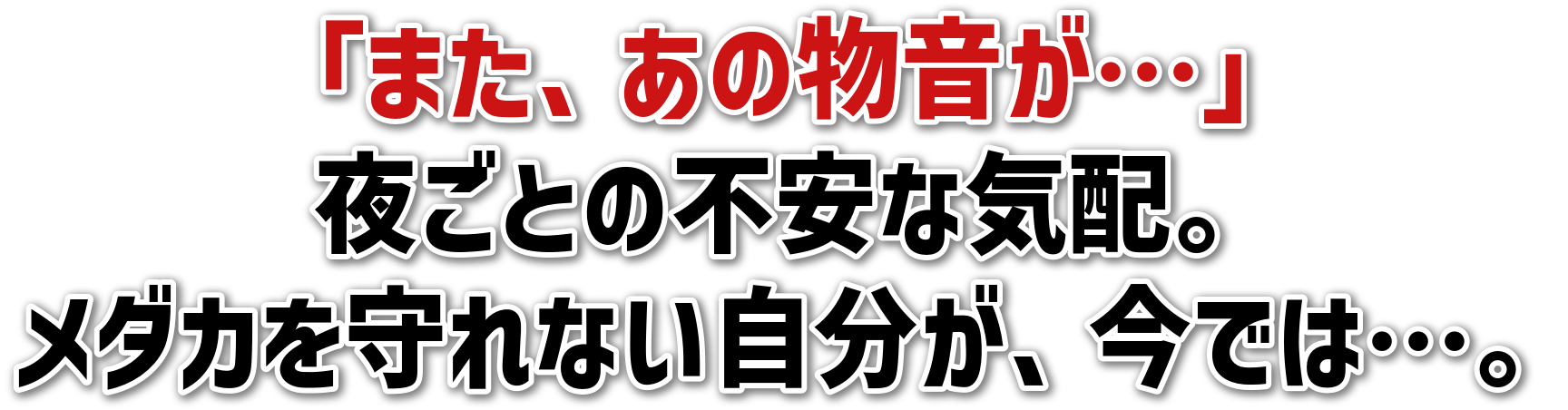
【この記事に書かれてあること】
大切に育てたメダカが、突然いなくなってしまった経験はありませんか?- アライグマは小型で捕まえやすいメダカを好んで狙う
- 夜間の池が特に被害に遭いやすい
- 効果的な対策にはネットやフェンスの設置がある
- 水位調整でアライグマの侵入を防ぐことができる
- 照明や超音波装置を活用した夜間の防衛策が有効
- ペパーミントの香りや猫砂の活用など意外な裏技も効果的
実は、その犯人がアライグマかもしれません。
アライグマは夜行性で、夜の池を狙う巧妙なハンターなんです。
でも、心配しないでください!
この記事では、アライグマによるメダカ被害の実態と、効果的な対策方法を詳しく解説します。
ネットやフェンスといった基本的な防衛法から、ペパーミントや猫砂を使った意外な裏技まで、10の秘策をご紹介。
愛するメダカを守るための知恵が、ここにあります!
【もくじ】
アライグマがメダカを狙う理由と被害の実態

アライグマはなぜメダカを好んで食べるのか?
アライグマがメダカを好んで食べる理由は、その手軽さと栄養価にあります。まず、メダカは小さくて動きが遅いため、アライグマにとって捕まえやすい絶好の獲物なんです。
「よーし、今日の夜ごはんはメダカにしよう!」とアライグマは考えているかもしれません。
アライグマの特徴をよく見てみましょう。
- 器用な前足:水中のメダカをすくい上げるのにぴったり
- 優れた夜間視力:暗闇でもメダカを見つけられる
- 雑食性:小魚も大好物
さらに、メダカは小さいながらも栄養価が高いんです。
「小さくても栄養満点!」というわけです。
アライグマにとっては、少ない労力で効率よく栄養を取れる理想的な食べ物なんです。
例えるなら、私たちにとってのポテトチップスのような存在かもしれません。
小さくて食べやすく、たくさん食べられちゃうんです。
「でも、他の魚はどうなの?」と思いますよね。
実は、アライグマは特別メダカだけを狙っているわけではありません。
ただ、メダカが最も捕まえやすいため、結果的によく食べられてしまうんです。
このように、アライグマにとってメダカは手軽で栄養満点の最高のごちそうなんです。
だからこそ、メダカを守るためには特別な対策が必要になってくるんです。
メダカ被害の深刻度!他の魚との比較
メダカ被害の深刻度は、他の魚と比べてもかなり高いんです。その理由を見ていきましょう。
まず、メダカの大きさが問題です。
メダカは体長が2〜4cm程度ととても小さいんです。
「小さいってことは、食べられる量も少ないんじゃない?」と思うかもしれません。
でも、そこが落とし穴なんです。
アライグマは一度にたくさんのメダカを捕食できちゃうんです。
例えるなら、私たちがポップコーンを一掴みで食べるようなものです。
「パクパクパク」とあっという間に多くのメダカが食べられてしまいます。
比較してみましょう。
- メダカ:小さくて数が多い → 一度に大量捕食
- 金魚:メダカより大きい → 捕まえにくい
- 鯉:さらに大きい → アライグマには手に負えない
また、メダカは浅い水辺を好む習性があります。
これがアライグマにとっては格好の狩り場になっちゃうんです。
「まるで並んで待っているようなもの」とアライグマは喜んでいるかもしれません。
さらに、メダカは夜間も活発に動き回ります。
これがアライグマの活動時間とぴったり重なるんです。
「夜の宴会場」のような状態になっちゃうんです。
経済的な面でも深刻です。
希少品種のメダカは1匹何万円もすることがあります。
「えっ、そんなに高いの?」と驚きますよね。
一晩でそんな大切なメダカがいなくなってしまうかもしれないんです。
このように、メダカ被害は他の魚と比べても特に深刻なんです。
だからこそ、しっかりとした対策が必要になってくるんです。
夜間の池が狙われやすい!アライグマの行動パターン
夜間の池がアライグマに狙われやすい理由は、アライグマの行動パターンにあります。そのパターンを知ることが、効果的な対策の第一歩なんです。
アライグマは典型的な夜行性動物です。
日が沈むとそわそわし始め、「さあ、狩りの時間だ!」と活動を開始します。
特に、日没後2〜4時間が最も活発な時間帯なんです。
アライグマの行動パターンを見てみましょう。
- 日中:木の洞や建物の隙間で休息
- 夕方:活動開始の準備
- 夜間:本格的な活動(餌探しや狩り)
- 明け方:再び隠れ場所へ
夜の池は、アライグマにとって理想的な狩り場なんです。
暗くて静かで、人間の目も届きにくい。
「ここなら安心して食事ができるぞ」とアライグマは考えているかもしれません。
さらに、アライグマの優れた夜間視力が有利に働きます。
暗闇でもメダカの動きを見つけられるんです。
まるで、夜間専用のフィッシングスポットのようなものです。
また、アライグマは学習能力が高いんです。
一度おいしい思いをした場所には、繰り返し訪れる傾向があります。
「あそこの池はごちそうがいっぱいだったな」と、記憶に残っているんです。
そして、アライグマは群れで行動することもあります。
「今日はみんなで宴会だ!」という具合に、複数のアライグマが同時に池を襲うこともあるんです。
このように、夜間の池はアライグマにとって絶好の餌場になっているんです。
だからこそ、夜間の対策がとても重要になってくるんです。
池の周りに明かりをつけたり、動きを感知するセンサーを設置したりするのも、効果的な方法の一つです。
メダカ被害は都市部と農村部どちらが多い?
メダカ被害は、実は農村部の方が都市部よりも多い傾向にあります。その理由を詳しく見ていきましょう。
まず、アライグマの生息環境を考えてみましょう。
- 農村部:自然が豊か、隠れ場所が多い
- 都市部:人工的な環境、隠れ場所が限られる
「ここなら思う存分暮らせるぞ!」とアライグマは喜んでいるかもしれません。
農村部の特徴を見てみましょう。
- 広い活動範囲:自由に動き回れる
- 豊富な食料源:果樹園や畑がたくさん
- 少ない人間の干渉:人目を気にせず行動できる
例えば、農村部の庭には often 池があります。
それも、広々とした自然に囲まれた池です。
アライグマにとっては「ごちそうの宝庫」のようなものです。
一方、都市部では人間の目が多く、アライグマの活動が制限されます。
「あっちにも人、こっちにも人!」とアライグマはストレスを感じているかもしれません。
また、農村部では家と家の距離が離れていることも影響します。
「誰も見ていないぞ、いただきま〜す!」とアライグマは安心して食事ができちゃうんです。
さらに、農村部の人々は often 自然と共生する意識が強いです。
「生き物だから仕方ない」と、アライグマの存在を許容してしまうこともあるんです。
ただし、都市部でも油断はできません。
公園や緑地があれば、そこからアライグマが侵入してくる可能性があります。
都市型アライグマは、人間の生活に適応する能力が高いんです。
このように、メダカ被害は農村部の方が多い傾向にありますが、都市部でも注意が必要です。
環境に合わせた適切な対策を取ることが大切なんです。
「餌付け」はメダカ被害を悪化させる大きな要因!
「餌付け」は、メダカ被害を悪化させる最大の要因の一つです。なぜそんなに悪いのか、詳しく見ていきましょう。
まず、餌付けの影響を考えてみましょう。
- アライグマが人間を恐れなくなる
- 特定の場所に繰り返し訪れるようになる
- アライグマの数が増える
例えば、「かわいそうだから」と思って食べ物を与えたとします。
アライグマは「ここは安全で食べ物がある場所だ!」と学習します。
そして、その場所に何度も訪れるようになるんです。
さらに悪いことに、アライグマは賢い動物です。
「人間=食べ物をくれる存在」と認識してしまうんです。
「こんにちは、今日のごはんは?」とばかりに、人間に近づいてくるようになっちゃいます。
餌付けの影響は、メダカだけにとどまりません。
- 庭の荒らし:花壇や野菜畑が被害に
- ゴミあさり:生ゴミを散らかす
- 家屋侵入:天井裏に住み着く
また、意図せず餌付けしてしまうケースもあります。
例えば、ペットのえさを外に置いたままにしたり、果樹の落果を放置したりすることです。
アライグマにとっては、これも立派な「餌場」になってしまうんです。
さらに、コンポストも要注意です。
生ゴミの臭いに誘われて、アライグマがやってくることがあります。
「今日の特選メニューは何かな?」とアライグマは喜んでいるかもしれません。
このように、餌付けはメダカ被害を悪化させる大きな要因なんです。
「かわいそうだから」という気持ちはわかりますが、結果的にアライグマにとっても、私たちにとっても良くないんです。
大切なのは、アライグマを寄せ付けない環境作りです。
食べ物を外に放置しない、ゴミ箱の蓋をしっかり閉める、果樹の管理をこまめにするなど、小さな心がけが大きな効果を生むんです。
効果的なメダカ保護対策と夜間の防衛策

池にネットを張る vs フェンスを設置する
池を守るなら、ネットとフェンス、どっちがいいの?結論から言うと、両方とも効果的ですが、状況によって使い分けるのがおすすめです。
まずはネットについて。
ネットは手軽で効果抜群なんです。
「えっ、そんな簡単なもので守れるの?」って思うかもしれませんね。
でも、アライグマの侵入を防ぐには、とっても有効な方法なんです。
ネットを使う時のポイントは3つ。
- 目の細かさ:2センチ四方以下のものを選ぶ
- 素材の強さ:ナイロンや金属製が良い
- 設置の仕方:池全体を覆い、隙間なく固定する
メダカも安心して泳げるわけです。
一方、フェンスはどうでしょう。
フェンスは見た目もスッキリして、庭の雰囲気を壊さない利点があります。
でも、設置には少し手間がかかるんです。
フェンスを選ぶ時のポイントは以下の通り。
- 高さ:1.5メートル以上
- 素材:ツルツルした金属やプラスチック
- 形状:上部を内側に折り曲げる
でも、どっちがいいの?
それは状況次第。
小さな池ならネット、大きな池ならフェンスがおすすめ。
「うちの池はどっちかな?」と迷ったら、まずはネットから試してみるのがいいかもしれません。
手軽に始められて、効果も抜群ですからね。
どちらを選んでも、大切なのは隙間をなくすこと。
ちょっとした隙間も、アライグマには絶好の侵入口になっちゃうんです。
がっちり守って、愛するメダカを守りましょう!
水位調整でアライグマの侵入を防ぐ!適切な水深とは
水位調整で、アライグマの侵入を防げるって知ってました?実は、水深を調整するだけで、メダカを守る強力な武器になるんです。
まず、アライグマが嫌がる水深について考えてみましょう。
アライグマは泳ぐのが得意ですが、深い水は苦手なんです。
「えっ、泳げるのに?」って思いますよね。
実は、アライグマは水に浸かるのを避ける傾向があるんです。
では、どのくらいの水深がいいのでしょうか?
- 最低でも40センチ以上
- できれば60センチ以上が理想的
- 岸辺から急に深くなるのがベスト
でも、ちょっと待って!
メダカにとっても快適な環境を作らないといけませんよね。
メダカは浅い水域を好むので、深すぎるのは問題です。
そこで、こんな工夫はどうでしょう。
- 池の一部を深くし、一部を浅く保つ
- 浅い部分にはネットを張る
- 水生植物を活用して隠れ場所を作る
水位調整には、もう一つ大事なポイントがあります。
それは、水位の変動です。
水位を時々変えることで、アライグマを混乱させることができるんです。
「昨日はここまで水があったのに、今日は違う!」とアライグマを戸惑わせるわけです。
ただし、急激な水位変更はメダカにストレスを与えるので注意が必要です。
ゆっくりと、少しずつ変えていくのがコツです。
水位調整は、他の対策と組み合わせるとさらに効果的。
例えば、深い水域と一緒にネットを使うと、アライグマは「深いし、ネットもあるし、もうダメだー」ってなっちゃいます。
メダカを守るのって、意外と奥が深いんです。
でも、こんな工夫をすれば、アライグマから大切なメダカを守れますよ。
水深を変えて、アライグマをびっくりさせちゃいましょう!
夜間照明 vs 超音波装置!どちらが効果的?
夜間のメダカ防衛、照明と超音波装置どっちがいいの?結論から言うと、両方とも効果的ですが、使い方次第でさらに威力アップ!
まず、夜間照明について。
アライグマは夜行性ですが、実は明るい場所が苦手なんです。
「え?夜行性なのに?」って思いますよね。
でも、突然の明るさには弱いんです。
効果的な照明の使い方は?
- 動きを感知して点灯するセンサーライト
- まぶしいLED電球を使用
- 池全体を照らせる位置に設置
一方、超音波装置はどうでしょう。
人間には聞こえない高い音を出して、アライグマを追い払う仕組みです。
「音が聞こえないのに効くの?」って不思議に思うかもしれません。
でも、アライグマには不快な音なんです。
超音波装置のポイントは?
- 20kHz以上の高周波を使用
- 動きを感知して作動するタイプを選ぶ
- 防水機能付きのものを選ぶ
でも、どっちがいいの?
実は、両方使うのがベストなんです。
光と音のダブルパンチで、アライグマを撃退!
「もう、この池には近づきたくない!」ってなっちゃうわけです。
使う時の注意点も。
照明は近所迷惑にならない明るさに、超音波は犬や猫にも影響があるので設置場所に気をつけましょう。
おまけの裏技!
照明や超音波装置を不規則に作動させるのも効果的。
「いつ光るかわからない」「いつ音が鳴るかわからない」って状況は、アライグマにとってはストレスなんです。
夜のメダカ池、明るく音で守れば安心。
アライグマさんごめんね、でもメダカは守らなきゃ!
ってことで、照明と超音波のコンボで、メダカを守りましょう!
室内への一時避難!メダカの安全を確保する最終手段
メダカを室内に避難させる?そう、これが最後の切り札になることもあるんです。
でも、いつどうやって行うべきか、しっかり知っておく必要がありますよ。
まず、室内避難が必要な状況を考えてみましょう。
- アライグマの出没が頻繁になった時
- 他の対策が全く効果を発揮しない時
- 特に貴重な品種のメダカを守りたい時
でも、急に室内に移すのは大変。
準備が必要です。
室内避難の手順を見てみましょう。
- 適切な大きさの水槽を用意する
- 水質を池の水に近づける
- 水温を合わせる
- メダカをそっと移す
- 十分な酸素を供給する
でも、メダカにとっては大きな環境変化なんです。
慎重に行わないと、ストレスで弱っちゃうかもしれません。
室内避難のメリットは完璧な安全性。
アライグマはおろか、他の天敵からも守れます。
でも、デメリットもあります。
毎日の水の管理や、日光不足の問題など、結構大変なんです。
ここで、ちょっとした工夫を紹介します。
全てのメダカを室内に入れるのは大変ですよね。
そこで、一部のメダカだけを室内に避難させるのはどうでしょう。
特に貴重な品種や、繁殖用のペアなどを選んで室内で守る。
これなら、管理の手間も減らせます。
また、避難期間も考えましょう。
「ずっと室内なの?」って心配になりますよね。
基本的には、アライグマの出没が落ち着くまでの一時的な措置です。
季節や地域によっても変わりますが、数週間から数ヶ月程度が目安になります。
室内避難は最終手段。
でも、知っておくと心強いですよね。
「もしもの時は、おうちの中においで」って、メダカに言ってあげられます。
大切なメダカを守るため、この方法も頭の片隅に置いておきましょう。
アライグマを寄せ付けない!庭の環境整備のコツ
庭の環境を整えるだけで、アライグマを寄せ付けない?そう、実はこれがとっても大切なんです。
アライグマが来たくなくなる庭作り、一緒に考えてみましょう。
まず、アライグマが庭に来る理由を考えてみましょう。
- 食べ物を探している
- 隠れ場所を探している
- 水場を求めている
では、具体的にどんなことをすればいいのでしょうか?
- 果物や野菜の収穫し忘れをなくす
- ゴミ箱はしっかり蓋をする
- コンポストは密閉型を使う
- 庭木は下枝を刈り込む
- 物置は隙間なくしっかり閉める
でも、これらの小さな工夫が、アライグマを寄せ付けない大きな力になるんです。
特に注意したいのが、意図しない餌付けです。
例えば、ペットのエサを外に置きっぱなしにしたり、バーベキューの残りを放置したり。
これらは、アライグマにとって「ごちそうさま!」のサインになっちゃうんです。
また、水場の管理も重要。
メダカ池以外の水たまりは、なるべくなくしましょう。
バケツや植木鉢の受け皿など、小さな水たまりもアライグマを誘う原因になります。
庭の照明も工夫のしどころ。
人感センサー付きのライトを設置すると、アライグマが近づいた時に「パッ」と明るくなって、びっくりさせることができます。
植栽の選び方も大切。
トゲのある植物や、強い香りのハーブ類を植えると、アライグマは「ちょっと近寄りにくいなー」って思うんです。
こうして環境を整えると、アライグマにとっては「あんまり魅力的じゃない庭」になります。
でも、人間にとっては快適な空間のままなんです。
庭の環境整備、ちょっとした工夫の積み重ねが大切。
「うちの庭、アライグマお断り!」って感じの空間を作って、メダカも人間も安心して過ごせる場所にしましょう。
驚きの裏技!メダカを守る5つの秘策

ペパーミントの香りでアライグマを撃退!植栽のコツ
ペパーミントの香りで、アライグマを寄せ付けない!?
実はこの方法、とても効果的なんです。
アライグマは鼻がとても敏感。
強い香りが苦手なんです。
特に、ペパーミントの爽やかな香りは「うわっ、くさい!」とアライグマを遠ざけてしまうんです。
では、どうやってペパーミントを活用すればいいのでしょうか?
- 池の周りにペパーミントを植える
- ペパーミントオイルを染み込ませた布を置く
- ペパーミントスプレーを作って散布する
- 日当たりの良い場所を選ぶ
- 水はけの良い土壌を用意する
- 定期的に刈り込んで香りを強く保つ
確かにその通りです。
でも、プランターに植えれば広がりすぎる心配もありません。
ペパーミントオイルを使う場合は、原液のまま使わないでくださいね。
水で薄めて、10%程度の濃度にするのがおすすめです。
「ちょっと強すぎたかな?」と思ったら、もう少し薄めてみましょう。
スプレーを作るなら、水100mlにペパーミントオイルを10滴程度入れるのがちょうどいいでしょう。
これを池の周りや、アライグマが通りそうな場所に吹きかけます。
ただし、直接メダカにかからないように注意してくださいね。
ペパーミントの香りは人間にとっては心地よいものです。
でも、アライグマにとっては「ここには近づきたくない!」というサインになるんです。
メダカを守りながら、庭も良い香りになる。
一石二鳥の対策、試してみませんか?
猫砂の意外な使い方!アライグマを寄せ付けない方法
猫砂でアライグマを撃退?意外ですが、これが結構効くんです!
アライグマは、実は猫を天敵だと認識しているんです。
「えっ、でも猫よりアライグマの方が大きいよね?」って思いますよね。
サイズは関係ないんです。
猫の存在を感じるだけで、アライグマは警戒心でいっぱいになっちゃうんです。
では、どうやって猫砂を使えばいいのでしょうか?
- 使用済みの猫砂を池の周りに撒く
- 猫砂を入れた布袋を設置する
- 猫砂と水を混ぜたペーストを作って塗る
- 新鮮なものを使う(古すぎると効果が薄れます)
- 雨に濡れないよう、屋根のある場所に置く
- 定期的に交換する(1週間に1回程度)
ペットショップで売っている未使用の猫砂でも効果はあります。
ただし、使用済みのものほど強力ではありません。
猫砂を入れた布袋を作るなら、古い靴下を利用するのがおすすめです。
穴の開いていない靴下に猫砂を詰めて、口をしっかり縛ります。
これを池の周りの木の枝にぶら下げたり、地面に置いたりします。
ペーストを作る場合は、猫砂と水を1:1の割合で混ぜます。
これを池の周りの木の幹や、フェンスに塗ります。
ただし、直接池の水に触れないよう注意してくださいね。
この方法、ちょっと変わっていますよね。
でも、アライグマにとっては「ここは猫のテリトリーだ!」というメッセージになるんです。
メダカを守るために、ちょっと意外な方法も試してみる価値ありですよ!
風船の揺れでアライグマを怯えさせる!設置のポイント
風船でアライグマを怖がらせる?これ、実は意外と効果的なんです!
アライグマは、予期せぬ動きや音に敏感なんです。
風船が風で揺れるたび「わっ、なんだ!?」ってびっくりしちゃうんです。
これを利用して、メダカを守る作戦を立てましょう。
では、どうやって風船を使えばいいのでしょうか?
- 池の上に風船を浮かべる
- 風船を紐でつるして池の周りに吊るす
- 風船の中に小石を入れて音を出す
- 複数の色を使う(視覚的効果を高める)
- 大きさを変える(予測不能な動きを作る)
- 定期的に位置を変える(慣れを防ぐ)
確かにその通りです。
でも、ゴム風船ではなくマイラー風船を使うと、長持ちするんです。
池の上に浮かべる場合は、風船を紐で軽い重りにつなぎます。
これで風で飛ばされることもありません。
「プカプカ」と浮かぶ風船を見て、アライグマは「なんだか怖いぞ...」と近づきにくくなるんです。
風船を紐でつるす時は、長さの異なる紐を使うのがコツです。
風が吹くたびに、それぞれの風船が違う動きをして「ふわふわ」揺れます。
これがアライグマには不気味に見えるんです。
小石を入れる場合は、米粒大の小石を2?3個入れるのがちょうどいいでしょう。
風が吹くたび「カラカラ」と音がして、アライグマを驚かせます。
この方法、見た目も楽しいですよね。
「庭が少しにぎやかになった!」なんて思えるかもしれません。
メダカを守りながら、庭の雰囲気も変わる。
一石二鳥の対策、ぜひ試してみてください!
CDの反射光を利用!アライグマを混乱させる裏技
古いCDが、まさかのアライグマ対策に大活躍!?
実はこれ、すごく効果的なんです。
アライグマは、突然の光の動きに敏感なんです。
CDの反射光が「キラキラ」と動くたび「うわっ、なんだ!?」って混乱しちゃうんです。
これを利用して、メダカを守る秘策を紹介しますね。
CDを使ったアライグマ対策、どんな方法があるでしょうか?
- CDを紐でつるして池の周りに吊るす
- CDを地面に立てて配置する
- CDを回転させる装置を作る
- 複数のCDを使う(効果を高める)
- 高さを変えて設置する(広範囲をカバー)
- 月明かりや街灯の光を利用する(夜間も効果を発揮)
確かにその通りです。
でも、定期的に新しいものと交換することで、効果を持続させることができます。
CDを紐でつるす場合は、釣り糸を使うのがおすすめです。
細くて目立たないので、庭の景観を損なわずに済みます。
風が吹くたびに「クルクル」と回って、アライグマを混乱させるんです。
地面に立てる時は、小さな杭を用意します。
CDの穴に杭を通して地面に刺せば、簡単に設置できます。
これを池の周りに数箇所配置すれば、「ここはなんだか怖い場所だ」とアライグマに思わせることができます。
回転させる装置を作るなら、小さなモーターとソーラーパネルを使います。
昼間は太陽光で充電し、夜になると自動的にCDが回転し始める仕組みです。
「ウィーン」と回るCDの動きに、アライグマは「うわー、何これ!?」ってパニックになっちゃうんです。
この方法、ちょっとユニークですよね。
「庭がディスコみたいになっちゃった!」なんて笑えるかもしれません。
でも、メダカを守るためならそれも悪くない。
楽しみながらアライグマ対策、始めてみませんか?
アンモニア水の活用法!アライグマが嫌う強烈な臭い
アンモニア水でアライグマを撃退?実はこれ、かなり効果的な方法なんです。
アライグマは、強烈な臭いが大の苦手。
特にアンモニアの刺激臭は「うぷっ、くさい!」と思わず逃げ出したくなるほどなんです。
この特性を利用して、メダカを守る作戦を立てましょう。
では、どうやってアンモニア水を使えばいいのでしょうか?
- アンモニア水を染み込ませた布を置く
- アンモニア水スプレーを作って散布する
- アンモニア水を入れた容器を設置する
- 必ず薄めて使用する(原液は危険です)
- 直接メダカや植物にかからないよう注意する
- 定期的に交換する(効果が薄れるため)
確かにその通りです。
だからこそ、使用する際は必ず安全に配慮しましょう。
布に染み込ませる場合は、アンモニア水を5倍に薄めたものを使います。
古いタオルや靴下に染み込ませ、ビニール袋に入れて穴を開けます。
これを池の周りの木の枝にぶら下げたり、地面に置いたりします。
スプレーを作る時は、水500mlに対してアンモニア水を大さじ1杯程度入れます。
これを池の周りや、アライグマが通りそうな場所に吹きかけます。
ただし、風上から吹きかけ、自分に臭いがかからないよう注意してくださいね。
容器を設置する場合は、小さなプラスチック容器にアンモニア水を入れ、蓋に小さな穴を開けます。
これを池の周りに数箇所配置します。
雨で薄まらないよう、屋根のある場所に置くのがポイントです。
この方法、ちょっと強烈ですよね。
「庭が変な臭いになっちゃった!」なんて思うかもしれません。
でも、メダカを守るためなら少しの我慢も必要です。
効果的なアライグマ対策、ぜひ試してみてください!