アライグマにサツマイモ畑を荒らされる?【地中の芋も掘り起こす】効果的な畑の防衛策3つを紹介

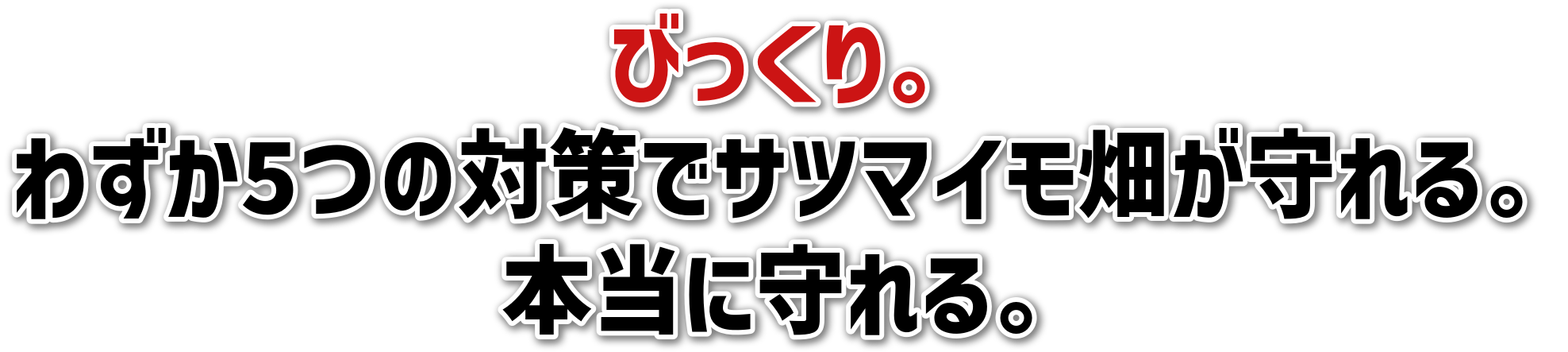
【この記事に書かれてあること】
愛情込めて育てたサツマイモ畑が、アライグマに荒らされてしまった経験はありませんか?- アライグマはサツマイモの高い栄養価に惹かれる
- 夜間の2?4時間が被害のピーク時間帯
- 電気柵や金網フェンスが効果的な物理的防御策
- 忌避剤の利用で臭いによる侵入防止が可能
- 早期収穫や深植えで被害リスクを軽減
夜な夜な畑を訪れるアライグマたちは、せっかく育てた作物を根こそぎ掘り起こしてしまいます。
収穫の喜びが絶望に変わる瞬間、何とかしたいですよね。
でも、大丈夫です!
この記事では、アライグマによるサツマイモ被害の特徴と、効果的な5つの対策方法をご紹介します。
これらの方法を実践すれば、被害を最大90%も減らすことができるんです。
さあ、アライグマとの知恵比べ、一緒に始めましょう!
【もくじ】
アライグマがサツマイモを好む理由と掘り起こし被害の特徴

アライグマの「サツマイモ好き」は栄養価が関係!
サツマイモの高い栄養価がアライグマを引き寄せています。アライグマはなぜサツマイモを好むのでしょうか?
それは、サツマイモの甘みと豊富な栄養素が関係しているんです。
アライグマは雑食性の動物ですが、特に高カロリーで栄養価の高い食べ物を好みます。
サツマイモはまさにぴったりの食べ物なんです。
「うわぁ、おいしそう!」とアライグマが喜ぶ理由がよくわかりますね。
サツマイモの魅力は次の3つです。
- 高カロリー:エネルギー源として最適
- 豊富な炭水化物:すぐに体力回復ができる
- ビタミンやミネラル:健康維持に役立つ
特に、冬に備えて体重を増やしたい時期には、サツマイモは格好の食べ物になります。
「でも、他の野菜はどうなの?」と思いますよね。
実は、アライグマは他の野菜よりもサツマイモを優先して食べる傾向があるんです。
それはサツマイモの栄養価が特に高いからなんです。
まるで「サツマイモ大好き!」と言っているかのようなアライグマの行動。
栄養たっぷりのサツマイモは、彼らにとって魅力的すぎる食べ物なんです。
だからこそ、サツマイモ畑を守るのは大変な作業になってしまうんです。
サツマイモ畑を狙う!アライグマの掘り起こし能力
アライグマの掘り起こし能力は驚くほど高く、サツマイモ畑に大きな被害をもたらします。その特徴をよく知ることが、効果的な対策の第一歩となるんです。
アライグマの前足は、まるで小さなスコップのよう。
鋭い爪と強い筋肉を使って、ゴリゴリと地面を掘り進めていきます。
「えい!えい!」と掘る姿が目に浮かびますね。
この能力を活かして、サツマイモを次々と掘り起こしていくんです。
アライグマの掘り起こし被害の特徴は以下の3つです。
- 深さ20〜30センチまで掘ることができる
- 畑の端や柵の近くから被害が始まる
- 穴を掘った跡が散在する
サツマイモは地中深くに育つので、アライグマの掘り起こし能力はちょうどいい具合なんです。
「やった!見つけた!」とアライグマが喜んでいるのが想像できますね。
被害の広がり方も特徴的です。
最初は畑の端や柵の近くから始まり、だんだん中心部へと広がっていきます。
まるで「少しずつ攻略していこう」という作戦を立てているかのようです。
畑全体に散在する穴跡を見ると、「まるで爆弾が落ちたみたい」と思ってしまうかもしれません。
それほど、アライグマの掘り起こし被害は深刻なんです。
このようなアライグマの能力を理解することで、より効果的な対策を立てることができます。
サツマイモ農家さんにとっては頭の痛い問題ですが、アライグマの特性を知ることが解決への第一歩となるんです。
地中の芋も見逃さない「アライグマの鋭い嗅覚」
アライグマの鋭い嗅覚は、地中に隠れたサツマイモも見逃しません。この嗅覚力がアライグマによる被害を深刻にしているんです。
アライグマの鼻は、まるで高性能センサーのよう。
地面の上を歩きながら、クンクンと匂いを嗅ぎ分けていきます。
「あれ?この下においしいものがあるぞ」と、地中のサツマイモの存在を察知してしまうんです。
アライグマの嗅覚の特徴は次の3つです。
- 土の中の匂いも感知できる
- サツマイモの甘い香りを遠くからも嗅ぎ取れる
- 熟したサツマイモを見分けられる
まるで「宝探しゲーム」をしているかのようですね。
特に熟したサツマイモの香りは、アライグマにとって「こっちにおいでー」と呼んでいるようなもの。
甘い香りに誘われて、どんどん畑の中に侵入してきてしまいます。
「でも、土に埋まっているのに匂いがするの?」と思うかもしれません。
実は、サツマイモが成長すると、その香りが土の表面にまで届くんです。
アライグマの鼻は、その微かな香りも見逃しません。
このアライグマの鋭い嗅覚を考えると、単に柵を設置するだけでは不十分かもしれません。
香りを遮断したり、別の強い匂いで誤魔化したりする対策も必要になってくるんです。
アライグマの鋭い嗅覚は、サツマイモ農家さんにとっては頭の痛い問題。
でも、この特性を理解することで、より効果的な対策を考えることができるんです。
匂いを利用した新しい防衛策が、今後の課題となりそうですね。
アライグマの被害は「夜間」に集中!要注意時間帯
アライグマによるサツマイモ畑への被害は、夜間に集中します。特に日没後2〜4時間が最も要注意な時間帯なんです。
アライグマは夜行性の動物。
昼間は木の洞や屋根裏でじっとしていますが、夕方になるとムクッと起き出します。
「さあ、今日も美味しいサツマイモを探しに行こう!」とばかりに、畑に向かって出発するんです。
アライグマの夜間活動の特徴は次の3つです。
- 日没直後から活動開始
- 真夜中まで活発に行動
- 明け方前に活動を終える
暗闇に紛れて、ごそごそと畑を荒らしていくんです。
「誰も見ていないから大丈夫」とでも思っているかのようですね。
特に注意が必要なのは、日没後2〜4時間の時間帯。
この時間、アライグマはお腹が空いて最も活発に動き回ります。
まるで「夜のサツマイモビュッフェ」が開催されているかのよう。
「でも、夜中に見回りに行くのは大変...」と思いますよね。
確かに、毎晩畑で見張りをするのは現実的ではありません。
そこで、この時間帯を狙った対策が重要になってくるんです。
例えば、動体センサー付きのライトを設置するのも一つの手。
アライグマが近づくと「パッ」と明るくなって、「わっ、見つかった!」とびっくりさせることができます。
また、タイマー式の音声装置を使うのも効果的。
夜間だけ「ワンワン!」と犬の鳴き声を流せば、アライグマも近づきにくくなるでしょう。
アライグマの夜行性を理解し、その活動時間帯に合わせた対策を立てることが大切。
夜の畑を守る新しい方法を考えてみるのも面白いかもしれませんね。
サツマイモ被害放置は「収穫皆無」のリスクあり!
アライグマによるサツマイモ被害を放置すると、最悪の場合、収穫が皆無になってしまうリスクがあります。早めの対策が極めて重要なんです。
被害を放置すると、アライグマの来訪頻度がどんどん増えていきます。
「ここにおいしいサツマイモがあるぞ!」という情報が、アライグマ社会に広まってしまうんです。
その結果、被害はあっという間に拡大していきます。
被害放置のリスクは次の3つです。
- 収穫量の激減:最悪の場合、全滅の可能性も
- 土壌の荒廃:掘り起こしで畑が荒れ果てる
- 周辺農地への被害拡大:隣の畑まで被害が及ぶ
アライグマは食べ残しをしません。
見つけたサツマイモは根こそぎ持っていってしまうんです。
「全部いただき!」とばかりに、畑を荒らし尽くしてしまいます。
土壌の荒廃も大きな問題。
アライグマが掘り起こした跡は、まるで「小さな陥没地帯」のよう。
この状態では、次の作付けにも影響が出てしまいます。
さらに厄介なのは、被害が周辺の農地にも広がっていくこと。
「隣の畑のサツマイモもおいしそう」と、アライグマの行動範囲がどんどん広がっていくんです。
「えー、そんなに深刻になるの?」と驚くかもしれません。
でも、実際にサツマイモ栽培を断念せざるを得なくなった農家さんもいるんです。
家庭菜園の楽しみが失われたり、地域の特産品としてのサツマイモが消滅したりする可能性すらあるんです。
だからこそ、早めの対策が大切。
アライグマの痕跡を見つけたら、すぐに行動を起こすことが重要です。
柵の設置や忌避剤の使用など、できることから始めていきましょう。
サツマイモ畑を守るのは大変な作業。
でも、美味しいサツマイモを守るためなら頑張る価値はあります。
アライグマと知恵比べをしながら、みんなで力を合わせて対策を考えていきましょう。
サツマイモ畑を守る!効果的なアライグマ対策法

「電気柵」vs「金網フェンス」アライグマ撃退力の差
サツマイモ畑を守るなら、電気柵が最強の味方です。アライグマ対策において、電気柵と金網フェンスには大きな差があるんです。
まず電気柵の威力からお話しましょう。
アライグマが電気柵に触れると「ビリッ」と軽い電気ショックを受けます。
これがトラウマとなって、二度と近づかなくなるんです。
「怖い!もうあそこには行かない!」とアライグマの頭に刻み込まれるわけです。
一方、金網フェンスはどうでしょうか。
確かに物理的な障壁にはなりますが、アライグマの驚くべき能力の前では、あまり効果がないんです。
なぜって?
- よじ登り上手:金網を器用によじ登ってしまいます
- 穴掘りの達人:フェンスの下を掘って侵入します
- 隙間発見のプロ:小さな隙間も見逃しません
でも、本当なんです。
アライグマの知恵と体の柔軟性を侮ってはいけません。
電気柵なら、高さ1.5メートル程度で十分な効果が期待できます。
でも金網フェンスの場合は、2メートル以上の高さが必要になってしまいます。
そして地面にも30センチほど埋め込む必要があるんです。
設置コストを考えると、電気柵の方が経済的。
そして何より、効果が圧倒的なんです。
「ビリッ」というちょっとした痛みが、アライグマに「ここは危険だ」という強烈な印象を与えるんです。
ただし、電気柵を設置する際は安全に十分注意しましょう。
人や他の動物に危険が及ばないよう、適切な電圧設定と設置場所の選択が重要です。
これさえ守れば、サツマイモ畑を守る最強の味方になってくれますよ。
香りで寄せ付けない!「忌避剤」の上手な使い方
アライグマの鼻を攻略すれば、サツマイモ畑を守れます。忌避剤を上手に使えば、アライグマを寄せ付けない環境づくりができるんです。
アライグマは鼻が敏感。
だからこそ、強い匂いが苦手なんです。
「うわっ、くさい!」とアライグマが思うような匂いを利用するのが、忌避剤の基本的な考え方です。
効果的な忌避剤の種類と使い方をご紹介しましょう。
- 天然オイル系:ペパーミントやユーカリのオイルが効果的
- 唐辛子系:辛さでアライグマを撃退
- アンモニア系:強烈な臭いでアライグマを遠ざける
- 市販の動物忌避剤:専門的に開発された製品も◎
畑の周りに忌避剤をまくことで、アライグマが越えたくない「見えない壁」を作るんです。
例えば、ペパーミントオイルを水で薄めて霧吹きに入れ、畑の周りの地面や植物にシュッシュッとスプレーします。
「ん?なんか変な匂いがする」とアライグマが立ち止まってくれるはずです。
唐辛子パウダーを水に溶かしたものも効果的。
地面にまいたり、布に染み込ませて畑の周りに吊るしたりします。
アライグマが「ヒリヒリする!」と感じて近寄らなくなるんです。
ただし、忌避剤だけに頼りすぎるのは禁物。
雨で流されたり、時間が経つと効果が薄れたりするので、定期的な再塗布が必要です。
また、人間や他の動物にも影響を与える可能性があるので、使用する際は注意が必要です。
忌避剤と他の対策法を組み合わせることで、より効果的なアライグマ対策ができます。
香りの壁で「ここは危険だぞ」とアライグマに警告を送りつつ、物理的な障壁も設けるなど、多層的な防御が理想的です。
サツマイモ畑を守る匂いの魔法、ぜひ試してみてくださいね。
畑の周囲に「緩衝地帯」を設置!侵入防止に効果的
アライグマを寄せ付けない秘策、それが「緩衝地帯」の設置です。サツマイモ畑の周りに一定の空間を作ることで、アライグマの侵入を防ぐことができるんです。
緩衝地帯とは、サツマイモ畑と周囲の環境の間に作る空き空間のこと。
この空間がアライグマにとっての「警戒ゾーン」になるんです。
「むむっ、なんだか開けすぎていて怖いぞ」とアライグマが感じてくれるわけです。
効果的な緩衝地帯の作り方をご紹介しましょう。
- 幅2〜3メートルの空間を確保
- 草刈りを定期的に行い、背の高い植物を除去
- 落ち葉や枝を取り除いてすっきりと
- 砂利や小石を敷き詰めるのも効果的
開けた場所は身を隠せないので、本能的に警戒してしまうんです。
さらに、砂利や小石を敷き詰めると効果アップ!
カサカサ、ゴロゴロという音がアライグマを不安にさせます。
「この音、なんだか怖いな」と足取りが鈍るんです。
緩衝地帯の内側に電気柵や金網フェンスを設置すれば、さらに強固な防御ラインの完成です。
アライグマは「ここは危険だ」と感じて、近づく気すら起きなくなるでしょう。
ただし、緩衝地帯を作る際は周囲の環境にも配慮が必要です。
急激な環境変化は生態系に影響を与える可能性があるので、少しずつ整備していくのがおすすめです。
また、定期的なメンテナンスも忘れずに。
草刈りや落ち葉の除去を怠ると、せっかくの緩衝地帯が台無しになってしまいます。
「よし、今日も畑の周りをきれいにしよう!」と、畑仕事の一環として取り組んでみてはいかがでしょうか。
緩衝地帯の設置、ちょっとした工夫でアライグマを寄せ付けない環境が作れるんです。
サツマイモ畑を守る新しい方法として、ぜひ取り入れてみてくださいね。
夜間の見回りとライトアップで「不安を与える」
アライグマに「ここは危険だぞ」と思わせる効果的な方法、それが夜間の見回りとライトアップです。これらの対策で、アライグマに不安を与え、サツマイモ畑への侵入を躊躇させることができるんです。
アライグマは夜行性。
暗闇に紛れて行動するのが得意なんです。
でも、人間が夜に活動していたり、明るい光が照らしていたりすると、「ん?なんだか様子がおかしいぞ」と警戒心を抱くんです。
効果的な夜間対策をご紹介しましょう。
- 定期的な見回り:2〜3時間おきが理想的
- 強力な懐中電灯で畑を照らす
- 動体センサー付きライトの設置
- ラジオなどの音源を置いて人の気配を演出
「わっ!人間だ!」とアライグマが驚いて逃げ出すでしょう。
動体センサー付きライトも強い味方です。
アライグマが近づくと「パッ」と明るく照らすので、「うわっ、見つかった!」と思わずビックリ。
これが繰り返されると、アライグマも「あそこは危険だ」と学習してくれるんです。
ラジオを置いておくのも効果的。
人の声が聞こえると「人間がいるぞ」と警戒します。
音量は小さめでOK。
むしろ小さな音の方が「誰かいるのかな?」とアライグマの好奇心と警戒心をくすぐるんです。
ただし、夜間の見回りには注意も必要です。
- 暗い中での転倒に気をつける
- 野生動物との不意の遭遇に備える
- 近隣への騒音配慮を忘れずに
確かに毎日は難しいかもしれません。
でも、週に2〜3回でも続けることで効果は十分にあります。
アライグマに「ここはいつ人間が来るかわからない」と思わせることが大切なんです。
夜間の見回りとライトアップ、ちょっとした工夫でアライグマを寄せ付けない環境が作れるんです。
他の対策と組み合わせて、サツマイモ畑を守る強力な防衛ラインを築いてくださいね。
サツマイモ栽培の工夫でアライグマ被害を軽減!

早期収穫で「アライグマの食べ頃」を回避!
サツマイモの早期収穫は、アライグマ被害を大幅に減らす効果的な方法です。アライグマが「美味しそう!」と思う前に収穫してしまうんです。
通常、サツマイモは植え付けから3〜4か月後に収穫します。
でも、アライグマ対策としては、少し早めの2〜3か月で収穫するのがおすすめです。
「えっ、そんなに早くていいの?」と思われるかもしれませんね。
早期収穫のメリットは次の3つです。
- アライグマの被害を避けられる
- 小ぶりだけど味の良いイモが収穫できる
- 収穫期間を分散できる
でも、「小さくてもおいしければいいじゃない!」という考え方で、むしろ味の良さを楽しめるんです。
収穫時期を分散させる方法も効果的です。
例えば、畑を3つに分けて、2週間ずつずらして植えるんです。
そうすれば、収穫も3回に分けられます。
「全部やられちゃった〜」というリスクが減らせますよ。
ただし、早すぎる収穫は味や栄養価に影響することもあります。
植え付けから2か月経ったら、時々様子を見て、適度な大きさになったものから収穫していくのがコツです。
「でも、収穫が早すぎて味が落ちそう...」と心配な方もいるでしょう。
そんな時は、収穫後のイモを1週間ほど温かい場所に置いておくんです。
これを「キュアリング」と呼びます。
芋の中の糖度が上がって、おいしくなるんですよ。
早期収穫は、アライグマとの知恵比べ。
彼らが「いただきま〜す」と言う前に、私たちが「ごちそうさま」と言ってしまうんです。
この作戦で、サツマイモ栽培の楽しみを取り戻しましょう!
「深植え」と「土寄せ」で掘り起こしを困難に!
アライグマの掘り起こし被害を防ぐ秘策、それが「深植え」と「土寄せ」です。これらの方法で、アライグマが「掘るの大変!」と諦めてくれるんです。
まず、深植えについて説明しましょう。
通常、サツマイモは10〜15センチの深さに植えます。
でも、アライグマ対策としては、20〜25センチの深さに植えるんです。
「そんなに深くて大丈夫?」と心配になるかもしれませんね。
深植えのメリットは次の3つです。
- アライグマの掘り起こしを困難にする
- 土壌水分の保持に役立つ
- イモの形が整いやすくなる
アライグマだって、「うーん、ちょっと深すぎるなあ」と諦めてしまうかもしれません。
次に、土寄せの重要性についてお話しします。
土寄せとは、苗の周りに土を盛り上げていく作業のこと。
これを定期的に行うことで、イモの上の土の層が厚くなるんです。
土寄せは、苗が15〜20センチほどに成長したら始めます。
その後、2週間おきくらいに行うのがおすすめです。
まるで、サツマイモの周りに小さな山を作るようなイメージですね。
土寄せのコツは、畝の高さを徐々に上げていくこと。
最終的には植え付け時より10〜15センチ高くなるようにします。
「よいしょ、よいしょ」と土を寄せていく作業は、ちょっとした運動にもなりますよ。
深植えと土寄せを組み合わせると、アライグマにとっては「ここを掘るのは大変そうだな」という難攻不落の要塞のようになるんです。
彼らも「こんなに苦労してまで掘るのはごめんだ」と思ってくれるはず。
ただし、深植えと土寄せをしすぎると、イモの生育に影響が出る可能性もあります。
様子を見ながら、バランスよく行うのがポイントです。
アライグマと知恵比べをしながら、美味しいサツマイモを育てていきましょう!
「ネット栽培」でサツマイモを守る新技術!
サツマイモを守る新しい方法として注目されているのが「ネット栽培」です。この方法なら、アライグマに「おいしそう!でも食べられない〜」とがっかりしてもらえるんです。
ネット栽培とは、サツマイモの苗を植える時に、周りを網で覆って育てる方法のこと。
まるでサツマイモにセーフティネットを張るようなものです。
「へえ、そんな方法があるんだ!」と驚かれるかもしれませんね。
ネット栽培のメリットは次の3つです。
- アライグマの掘り起こしを物理的に防ぐ
- イモの形が整いやすくなる
- 収穫が楽になる
穴の大きさが2〜3センチ四方くらいのものを選びましょう。
アライグマの手が入らない大きさです。
ネットの設置方法は簡単。
まず、畝を作ったら、その上にネットを広げます。
次に、ネットの上から苗を植えていきます。
最後に、ネットの端を土で覆って固定すれば完成です。
「よし、これで安心だ!」という気分になりますよ。
ネットの中でイモが成長していくので、アライグマが掘り起こそうとしても「あれ?なんか掘れないぞ」となるわけです。
まるで、サツマイモに鎧を着せているようなものですね。
さらに、ネット栽培には思わぬメリットも。
イモの形が整いやすくなるんです。
ネットの目を基準に成長するので、きれいな形のイモができやすくなります。
「見た目もよくて、アライグマ対策にもなる」という一石二鳥の効果があるんです。
収穫時も楽チンです。
ネットごと引き上げれば、イモが一気に収穫できます。
「ほら、こんなにたくさんできたよ!」と、収穫の喜びも倍増しそうですね。
ただし、注意点もあります。
ネットが土に埋まりすぎると、イモの成長を妨げる可能性があります。
定期的にネットの状態を確認して、必要に応じて調整しましょう。
ネット栽培、ちょっと手間はかかりますが、アライグマ対策としては効果抜群。
「今年こそはたくさん収穫するぞ!」という意気込みで、ぜひ試してみてください。
周辺作物で「囮」作戦!被害を分散させる方法
アライグマの被害を軽減する意外な方法、それが「囮作戦」です。サツマイモの周りに別の作物を植えて、アライグマの注意を分散させるんです。
「えっ、わざと食べられる作物を植えるの?」と驚く人もいるかもしれません。
この作戦のポイントは、サツマイモよりも魅力的な作物を周りに植えること。
アライグマに「こっちの方がおいしそう!」と思わせるんです。
囮作戦に適した作物は次の3つです。
- トウモロコシ:甘くて栄養価が高い
- カボチャ:大きくて食べ応えがある
- スイカ:水分が多くて魅力的
「おっ、あっちにもおいしそうなものがあるぞ!」とアライグマが思ってくれるわけです。
トウモロコシは特に効果的です。
アライグマはトウモロコシの甘い実が大好物。
サツマイモ畑の外側にトウモロコシを植えれば、アライグマは「こっちの方が簡単に食べられるぞ」と、そちらに向かう可能性が高くなります。
カボチャも良い選択肢です。
大きくて目立つので、アライグマの目を引きやすいんです。
「わあ、あんなに大きいの見つけた!」とアライグマが喜んでくれるかもしれません。
スイカも水分が多くて魅力的。
特に暑い季節は、アライグマも喉が渇いているはず。
「ああ、のどが渇いた〜」というアライグマの気持ちを利用するわけです。
ただし、注意点もあります。
囮作物も被害を受ける可能性があるので、完全な解決策ではありません。
また、アライグマの数が増えすぎないよう、餌付けにならない程度に調整することが大切です。
囮作戦は、アライグマとの「平和共存」を目指す方法とも言えます。
「全部食べられちゃうよりはマシ」という考え方で、被害を分散させるんです。
サツマイモを守りつつ、畑全体の生態系バランスを保つ。
そんな賢い農家になれるかもしれませんよ。
「品種選び」も重要!アライグマに狙われにくい特徴
サツマイモの品種選びも、実はアライグマ対策の重要なポイントなんです。「え?サツマイモにそんな違いがあるの?」と思われるかもしれませんね。
実は、アライグマに狙われにくい特徴を持つ品種があるんです。
アライグマに狙われにくいサツマイモの特徴は、主に次の3つです。
- 甘みが控えめな品種
- 皮が厚くて硬い品種
- 深く成長する品種
アライグマは甘いものが大好き。
だから、甘みの強い品種ほど狙われやすいんです。
「甘くないサツマイモなんてあるの?」と疑問に思うかもしれません。
でも、実際にあるんです。
例えば、「ベニアズマ」という品種は、比較的甘みが控えめ。
また、「タマユタカ」も甘さはそれほど強くありません。
これらの品種なら、アライグマに「うーん、ちょっと物足りないな」と思わせることができるかもしれません。
次に、皮が厚くて硬い品種。
これは、アライグマが掘り起こしても、すぐには食べられないという利点があります。
「シロユタカ」という品種は、皮が比較的厚いので、アライグマの被害を受けにくいと言われています。
最後に、深く成長する品種。
これは、アライグマの掘る能力を超えた深さまでイモが成長するんです。
「ベニハルカ」という品種は、比較的深くまで成長するので、アライグマの手が届きにくいんです。
ただし、注意点もあります。
これらの品種は、味や収穫量の面で一般的な品種と違いがある場合があります。
また、地域の気候に合わない場合もあるので、専門家や経験豊富な農家さんに相談するのがいいでしょう。
品種選びは、アライグマとの知恵比べの一環。
「よーし、今年はアライグマに負けないぞ!」という気持ちで、新しい品種にチャレンジしてみるのも面白いかもしれません。
美味しさと防衛力、両方を兼ね備えたサツマイモ栽培。
それが、アライグマと共存する新しい農業の形かもしれませんね。