日本に生息するアライグマの大きさは?【体長40?60cm、体重4?9kg】侵入可能な隙間のサイズに要注意

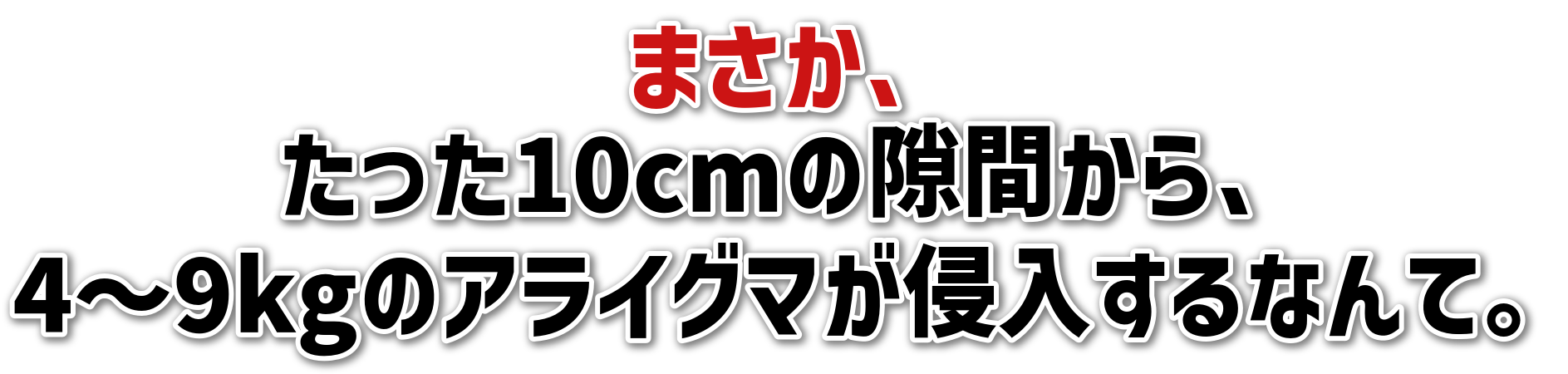
【この記事に書かれてあること】
アライグマの大きさ、想像以上かもしれません。- 日本のアライグマは体長40〜60cm、体重4〜9kgと意外と大きい
- オスとメスで体格差があり、オスの方が大きく重い
- 成長が早く、生後1年で成体サイズに到達する
- 10cmの隙間からでも侵入可能なため要注意
- 体格を知ることで効果的な被害対策が可能になる
体長40〜60センチ、体重4〜9キロ。
これが日本に生息するアライグマの平均的な体格なんです。
「えっ、そんなに大きいの?」と驚く方も多いはず。
実は、この体格が家屋への侵入や被害の原因になっているんです。
オスとメスで体格差があり、成長も早い。
さらに、なんと10センチの隙間からでも侵入可能!
アライグマの体格を正しく理解することが、効果的な被害対策の第一歩。
この記事では、アライグマの体格の特徴と、それを踏まえた具体的な対策方法をご紹介します。
【もくじ】
アライグマの体格を知る!被害対策の第一歩

日本のアライグマは体長50cm!意外と大きな体格に注意
日本のアライグマの体長は平均50cmほど。これは意外と大きいんです。
「えっ、そんなに大きいの?」と驚く方も多いはず。
実はこの大きさ、被害対策を考える上でとても重要なポイントなんです。
アライグマの体長を知ることで、どんな対策が必要か見えてきます。
例えば、50cmの体長があれば、家の中のかなり狭い場所にも入り込める可能性があります。
「うちの天井裏なんて、そんな大きな動物は入れないでしょ」なんて油断は禁物。
実は天井裏は絶好の隠れ家になっちゃうんです。
体長を知ることで、次のような対策が必要だとわかります:
- 天井裏や床下の隙間を5cm以下に狭める
- 庭の柵を1.5m以上の高さにする
- 物置や倉庫の扉をしっかり閉める
- ゴミ箱は蓋付きで重いものを選ぶ
そうすれば、事前に対策を打てて、被害を防げる可能性がグッと高まるというわけです。
体重は4〜9kg!想像以上の重さで家屋被害の可能性も
アライグマの体重は4〜9kgもあるんです。「えっ、猫くらいの大きさなのに、そんなに重いの?」と思われるかもしれません。
でも、この重さが家屋被害につながる可能性があるんです。
アライグマの体重を知ることで、次のような被害が想像できます:
- 屋根に上ると、瓦がズレる可能性
- 天井裏を歩き回って、天井板が抜ける危険性
- 庭の植木鉢を倒して割ってしまうこと
- ゴミ箱を簡単にひっくり返せる力
アライグマが家の中を歩き回っている可能性があります。
体重があるため、その足音はかなり大きいんです。
また、この体重を生かしてアライグマは器用に行動します。
例えば、体重をかけてゴミ箱の蓋を開けたり、体当たりして扉を開けたりすることも。
「こんな重い蓋、開けられるわけない」なんて油断は禁物です。
対策としては、次のようなものが効果的です:
- 屋根や天井の補強工事を検討
- ゴミ箱は10kg以上の重さに耐えられるものを選ぶ
- 庭の装飾品は安定性の高いものを使用
「重さ」を侮らず、しっかりと備えることが大切なんです。
オスとメスで体格差あり!最大2kgの体重差に驚き
アライグマはオスとメスで体格差があるんです。なんと、最大で2kgもの体重差があることも。
「えっ、そんなに違うの?」と驚く方も多いはず。
この体格差を知ることで、より効果的な対策が立てられるんです。
まず、体格差の詳細を見てみましょう:
- オス:体重6〜9kg、体長50〜60cm
- メス:体重4〜7kg、体長45〜55cm
この差は、アライグマの行動や被害の特徴に影響します。
例えば、オスは体が大きいため、より高い場所に登ったり、重い物を動かしたりする力があります。
「屋根の上にアライグマがいる!」なんて状況は、大抵オスの仕業かもしれません。
一方、メスは体が小さいので、狭い隙間にも入り込みやすいんです。
「こんな小さな穴、入れるわけない」と思っても、メスなら入れちゃうかも。
この体格差を考慮した対策を立てると、より効果的です:
- 屋根や高所の対策はオスの体格を基準に
- 小さな隙間の封鎖はメスの体格を基準に
- 捕獲用の罠は両方のサイズに対応できるものを
逆に、「カサカサ」という小さな音なら、メスかもしれません。
体格差を知ることで、「この被害はオスかな?メスかな?」と推測できるようになります。
そうすれば、より的確な対策が立てられるというわけです。
アライグマの体格差、侮れないですよ!
成長が早い!生後1年で成体サイズに到達する特徴
アライグマの成長スピードは驚くほど速いんです。なんと、生まれてから1年で成体とほぼ同じサイズになっちゃいます。
「えっ、そんなに早く大きくなるの?」と驚く方も多いはず。
この特徴を知ることで、被害対策の重要性がより理解できるんです。
アライグマの成長過程を見てみましょう:
- 生まれたての赤ちゃん:体重約100g、体長約15cm
- 生後2か月:体重約1kg、体長約30cm
- 生後6か月:体重約3kg、体長約40cm
- 生後1年:体重4〜9kg、体長40〜60cm(成体サイズ)
「ほら、小さいアライグマがいるよ。かわいいな〜」なんて油断していると、あっという間に大きくなっちゃうんです。
この急成長が被害対策を難しくする原因になっています。
例えば、「この隙間なら大丈夫」と思っていても、数か月後には入れるサイズになっているかも。
「この軽い蓋なら開けられないでしょ」と安心していても、すぐに開けられる力を持つようになるんです。
だからこそ、次のような対策が重要になります:
- 見つけたらすぐに対策を講じる
- 小さな個体がいても油断しない
- 対策は成体サイズを基準に行う
- 定期的に対策の見直しをする
数か月後には「ドタドタ」「ガサガサ」という大きな音に変わっているかもしれません。
アライグマの急成長を知ることで、「今のうちに対策しておこう」という意識が高まります。
小さな個体を見つけても油断せず、すぐに行動することが大切なんです。
成長スピードを侮らないでください!
10cmの隙間でも侵入可能!「小さい」は危険な思い込み
アライグマは、なんと直径10cmほどの小さな隙間からでも侵入できてしまうんです。「えっ、そんな小さな隙間から?」と驚く方も多いはず。
この能力を知ることで、より効果的な侵入防止対策が立てられるんです。
アライグマがこんな小さな隙間から入れる理由は、その体の特徴にあります:
- 柔軟な体:骨格が柔らかく、体を細くできる
- 頭蓋骨の形状:頭が通れば体も通れる構造
- 鋭い爪:隙間を広げたり、つかまったりするのに便利
この能力が、家屋への侵入を容易にしています。
例えば、屋根の小さな隙間、換気口、配管の周り、これらすべてがアライグマにとっては「入口」になり得るんです。
「こんな小さな隙間、大丈夫でしょ」なんて油断は禁物です。
そのため、次のような対策が重要になります:
- 6cm未満の隙間にまで注意を払う
- 屋根や外壁の細かいチェックを定期的に行う
- 換気口や配管周りに金属製の網を取り付ける
- ドアや窓の隙間も要チェック
小さな隙間から侵入したアライグマかもしれません。
アライグマの侵入能力を知ることで、「ここも塞がなきゃ」という意識が高まります。
小さな隙間も侮らず、しっかりと対策することが大切なんです。
10cmの隙間、あなたの家にはありませんか?
今すぐチェックしてみましょう!
アライグマの体格を徹底比較!被害予防のヒント

アライグマvs猫!意外と大きな体格差に要注意
アライグマは、一般的な猫よりもずっと大きいんです。この体格差を知ることで、アライグマの被害対策がより効果的になります。
まず、サイズを比べてみましょう。
普通の猫の体長は約40〜50センチ、体重は3〜5キロ程度です。
一方、アライグマは体長50〜60センチ、体重4〜9キロもあるんです。
「えっ、そんなに違うの?」と驚く方も多いはず。
この体格差が、アライグマの被害を深刻にしているんです。
例えば:
- 猫用のペットドアから簡単に侵入できてしまう
- 猫よりも高い場所に到達できる
- 猫用の柵や網では防ぎきれない
- 猫以上の力で物を倒したり壊したりする
アライグマは猫用の設備をいとも簡単に突破しちゃうんです。
対策としては、次のようなことが効果的です:
- ペットドアをアライグマ侵入防止タイプに交換する
- 柵や網の高さを1.5メートル以上に上げる
- 庭の装飾品や植木鉢をより安定性の高いものに変える
そうすれば、早めの対策で被害を最小限に抑えられるというわけです。
猫以上の用心が必要、それがアライグマ対策の基本なんです!
タヌキとの違いは?体格で見分ける方法を解説
アライグマとタヌキ、見た目は似ているけど、体格には大きな違いがあるんです。この違いを知ることで、適切な対策が立てられます。
まずは、サイズの比較から見てみましょう:
- アライグマ:体長50〜60センチ、体重4〜9キロ
- タヌキ:体長45〜55センチ、体重4〜7キロ
「えっ、そんなに変わらないじゃん」と思うかもしれません。
でも、この小さな差が大きな違いを生むんです。
例えば、アライグマはタヌキよりも:
- 高い場所に登る能力が高い
- 力が強く、物を壊す被害が大きい
- 手先が器用で、複雑な仕掛けも開けてしまう
- 跳躍力が高く、より高い柵も乗り越えられる
アライグマはタヌキ用の対策をいとも簡単に突破しちゃうんです。
体格の違いを知ることで、次のような対策が効果的になります:
- 柵の高さを1.5メートル以上に設定
- ゴミ箱はより頑丈なものを選ぶ
- 屋根や壁の隙間をより小さく塞ぐ
すぐに「もしかして…」と気づけるようになれば、早めの対策で被害を防げるというわけ。
タヌキ以上の警戒が必要、それがアライグマ対策の要なんです!
中型犬と同等サイズ!ペットとの遭遇に警戒を
アライグマの体格は、なんと中型犬とほぼ同じなんです。この事実を知ることで、ペットとアライグマの遭遇時の危険性がよくわかります。
まずは、サイズを比較してみましょう:
- アライグマ:体長50〜60センチ、体重4〜9キロ
- 中型犬(例:柴犬):体長50〜55センチ、体重8〜11キロ
この体格の近さが、ペットにとって大きな脅威になるんです。
アライグマと中型犬が似ているサイズだからこそ、次のような危険があります:
- ペットと互角に渡り合える力がある
- ペットの餌や寝床を奪う可能性がある
- ペットドアから簡単に侵入できてしまう
- 庭でペットと遭遇する可能性が高い
アライグマは野生動物なので、ペットよりも攻撃的になる可能性が高いんです。
体格の近さを知ることで、次のような対策が重要になります:
- ペットの夜間の外出を控える
- 庭にペット用の安全なスペースを作る
- ペットドアを夜間は閉めるか、アライグマ侵入防止タイプに交換
- ペットフードは屋内で保管し、食べ終わったらすぐに片付ける
すぐに「もしかして…」と気づけるようになれば、早めの対処で大事に至らずに済むというわけ。
ペットの安全を守るため、アライグマの体格を侮らないことが大切なんです!
体重と破壊力の関係!4〜9kgの重さが引き起こす被害
アライグマの体重4〜9キロ、この重さが予想以上の破壊力を生むんです。この関係を理解することで、より効果的な被害対策が立てられます。
まず、アライグマの体重がもたらす影響を見てみましょう:
- 屋根瓦のズレや破損
- 天井裏の断熱材の圧縮や破壊
- 庭の植木鉢や装飾品の転倒
- ゴミ箱の転倒や中身の散乱
でも、この重さが動き回ることで、想像以上の被害を引き起こすんです。
例えば、こんな状況を想像してみてください:
- 屋根の上をドタドタと歩き回る音
- 天井裏でガサゴソと動き回る気配
- 庭でガチャンと何かが倒れる音
- 深夜にガラガラとゴミ箱をひっくり返す音
この体重と破壊力の関係を知ることで、次のような対策が効果的になります:
- 屋根や天井裏の補強工事を検討
- 庭の装飾品は重心の低いものを選ぶ
- ゴミ箱は10キロ以上の重さに耐えられるものを使用
- 家の周りに動体センサー付きライトを設置
4〜9キロの重さが引き起こす被害を侮らず、しっかりと対策を立てることが大切なんです。
あなたの家は、この重さに耐えられますか?
今一度、チェックしてみましょう!
季節による体格変化!冬に向けて太る習性を把握
アライグマの体格は、季節によって大きく変化するんです。特に冬に向けて太る習性があり、この変化を知ることで、より効果的な対策が立てられます。
まず、季節による体重変化を見てみましょう:
- 春〜夏:標準体重(4〜7キロ程度)
- 秋:徐々に増加(5〜8キロ程度)
- 冬:最大体重(6〜9キロ以上)
この体重変化が、季節ごとの被害の特徴を生み出すんです。
例えば、季節ごとにこんな違いが出てきます:
- 春〜夏:活発に動き回り、広範囲に被害が及ぶ
- 秋:食欲が増し、庭や農作物への被害が増える
- 冬:体重が重くなり、家屋への負担が大きくなる
実は、アライグマは冬眠しないので、一年中活動しているんです。
この季節による体格変化を知ることで、次のような対策が効果的になります:
- 秋には庭や農作物の防御を強化
- 冬に向けて屋根や天井裏の耐久性を確認
- 春〜夏は広範囲にわたる対策を実施
- 年間を通じて食料源となるものを管理
季節ごとの体格変化を把握することで、「今の時期はこんな対策が必要だ」と、先手を打てるようになるというわけ。
季節に応じた対策で、年間を通じてアライグマ被害から家を守りましょう!
アライグマの体格を知って被害対策!5つの効果的方法

体格モデルで侵入口チェック!簡単DIYで対策強化
アライグマの体格を模した簡単な模型を作ることで、家の周りの侵入口を効果的にチェックできます。これは意外と簡単で、とても役立つんです。
まず、アライグマの体格モデルを作りましょう。
段ボールや発泡スチロールで、体長50センチ、直径10センチくらいの筒を作ります。
「えっ、そんな大きさなの?」と驚く方も多いはず。
でも、これがアライグマの平均的な大きさなんです。
このモデルを使って、家の周りをチェックしていきます。
例えば:
- 屋根裏への換気口や隙間
- 床下への侵入口や通気口
- 壁の亀裂や隙間
- 窓やドアのすき間
「ギュウギュウ」とモデルを押し込んでみて、通れそうなら要注意。
この方法のいいところは、目で見るだけでは気づかない侵入口も見つけられること。
「こんな小さな隙間、大丈夫でしょ」なんて油断は禁物です。
アライグマは意外と柔軟な体を持っているんです。
見つけた隙間は、すぐに対策を。
例えば:
- 金網や板で塞ぐ
- 隙間を埋める材料で充填
- 強固な金属製のカバーを取り付ける
「ちょっとした工夫で、こんなに効果があるなんて!」と、きっと驚くはず。
体格モデルを使ったチェック、ぜひ試してみてくださいね。
体重を意識した柵選び!4〜9kgに耐える素材がカギ
アライグマの体重は4〜9キロもあるんです。この重さを意識して柵を選ぶことで、効果的な侵入防止ができます。
まず、アライグマの体重をイメージしてみましょう。
4〜9キロというと、大きめのスイカくらいの重さです。
「えっ、そんなに重いの?」と驚く方も多いはず。
この重さが、柵選びのポイントになるんです。
アライグマはこの体重を活かして、次のような行動をとります:
- 柵をよじ登る
- 体重をかけて押し倒す
- 柵の隙間を広げる
- 強度:9キロ以上の重さに耐えられる素材
- 高さ:1.5メートル以上(登られにくい)
- 目の細かさ:5センチ以下の隙間(体が通れない)
- 埋め込み深さ:30センチ以上(掘り返されにくい)
金属製のものが一番おすすめ。
「プラスチック製なら安いし…」なんて考えはやめましょう。
アライグマの歯や爪は意外と強いんです。
設置方法も工夫が必要です:
- 柵の上部を外側に傾ける(よじ登りにくくなる)
- 電気柵を組み合わせる(触れると軽い電気ショック)
- 柵の周りに砂利や小石を敷く(歩きにくくなる)
でも、適切な柵を選んでいれば安心です。
体重を意識した柵選び、ちょっとした工夫で大きな効果が得られます。
アライグマの侵入を防ぐ強い味方、それが適切な柵なんです。
10cm未満の隙間を全てふさぐ!確実な侵入防止策
アライグマは驚くほど小さな隙間から侵入できるんです。なんと、直径10センチの穴さえあれば入り込めてしまいます。
だから、10センチ未満の隙間を全てふさぐことが、確実な侵入防止策になるんです。
「えっ、そんな小さな隙間から入れるの?」と驚く方も多いはず。
でも、アライグマの体は意外と柔軟なんです。
頭が通れれば、体も通れちゃうんです。
まず、家の周りをよく観察してみましょう。
こんな場所に要注意です:
- 屋根と壁の接合部
- 換気口や排水口
- 窓やドアの隙間
- 配管や電線の通り道
- 古い建物の亀裂や穴
隙間をふさぐ方法はいろいろあります:
- 金属製の網や板で覆う
- 専用の充填材で埋める
- セメントやモルタルで塞ぐ
- 隙間テープやシーリング材を使う
「プラスチックなら安いし…」なんて考えは危険です。
アライグマは予想以上に力が強いんです。
また、定期的なチェックも忘れずに。
「一度ふさいだから大丈夫」なんて油断は禁物。
時間が経つと新たな隙間ができることもあるんです。
「カサカサ」「ガリガリ」という音が聞こえたら要注意。
アライグマが侵入しようとしている可能性があります。
でも、10センチ未満の隙間を全てふさいでおけば、安心して眠れるはず。
小さな隙間をふさぐ、この地道な作業が実は最強の対策なんです。
アライグマとの知恵比べ、負けないようにしっかり対策しましょう!
ゴミ箱に重り設置!アライグマの体重以上で安全確保
アライグマの体重は4〜9キロ。この重さを超える重りをゴミ箱に設置することで、効果的に荒らしを防げます。
意外と簡単なこの方法、試してみる価値ありですよ。
まず、アライグマがゴミ箱を荒らす様子を想像してみてください。
「ガタガタ」「ドタバタ」と音を立てながら、ゴミ箱をひっくり返そうとします。
でも、ゴミ箱が重くて動かない。
そんな状況を作り出すんです。
重りの選び方がポイントです。
例えば:
- レンガや石:10キロ以上のものを選ぶ
- 砂袋:中身の量で重さを調整できる
- 金属製のウェイト:見た目もすっきり
- 水を入れたペットボトル:手軽で経済的
でも、アライグマは予想以上に力が強いんです。
自分の体重以上のものでも、ひっくり返せることがあるんです。
重りの設置場所も重要です:
- ゴミ箱の蓋の上に置く
- ゴミ箱の底に固定する
- ゴミ箱を固定具で地面に固定し、さらに重りを乗せる
- ゴミ箱を金属製のケージで囲む
- チェーンでゴミ箱を固定する
- 蓋がロックできるタイプのゴミ箱を使う
一石二鳥の対策なんです。
「ガサゴソ」という音が聞こえても、もう心配ありません。
重りつきのゴミ箱なら、アライグマもお手上げ。
「こんな簡単なことで、こんなに効果があるなんて!」きっと驚くはずです。
ゴミ箱への重り設置、ちょっとした工夫で大きな効果が得られる、おすすめの対策方法です。
試してみる価値、十分ありますよ!
体長を考慮したトラップ設置!効果的な捕獲方法とは
アライグマの体長は40〜60センチ。この大きさを考慮したトラップを設置することで、効果的な捕獲ができます。
正しい設置方法を知れば、アライグマ対策の強い味方になりますよ。
まず、適切なトラップのサイズを選びましょう。
アライグマの体長を考えると:
- 長さ:70〜80センチ以上
- 幅:25〜30センチ以上
- 高さ:30〜35センチ以上
でも、アライグマが楽に入れる大きさでないと、警戒して近づかないんです。
トラップの種類も重要です:
- 箱型トラップ:最も一般的で使いやすい
- 両開きトラップ:捕獲効率が高い
- 囲いわな:複数匹を一度に捕獲可能
アライグマの行動パターンを考えて:
- 家屋への侵入経路付近
- 餌場になっている場所の近く
- アライグマの足跡や糞が見られる場所
- 建物の隅や壁沿い
アライグマの大好物を使いましょう:
- 魚の缶詰(特にサバやイワシ)
- 果物(メロンやイチゴなど)
- マシュマロやピーナッツバター
でも、捕獲後の対応は慎重に。
むやみに近づいたり触ったりするのは危険です。
体長を考慮したトラップ設置、正しい方法を知ればとても効果的。
でも、トラップを使う際は必ず地域の規則を確認してくださいね。
適切な使用で、アライグマ被害から家を守りましょう!